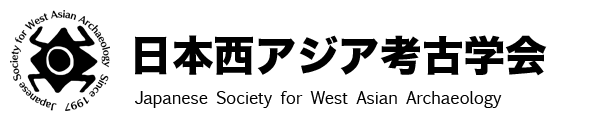2028年2月28日開催講演会:メソポタミアの初期王朝時代の首都、キシュ
講演会の案内をいただきましたので、お知らせします。
*********************************
古代オリエント博物館では現在、クローズアップ展「キシュ:メソポタミアの都市遺跡を掘る」を開催中です(3月29日まで)。
https://aom-tokyo.com/exhibition/260214_kish.html
その関連行事として、講演会「メソポタミアの初期王朝時代の首都、キシュ」を2月28日(土)に開催します。ふるってご参加ください。
日時:2026年2月28日(土)13:30~15:00
講師:小口 和美(国士舘大学21世紀アジア学部附属イラク古代文化研究所所長・教授)
開催形態:対面開催のみ(オンライン配信はありません)
会場:池袋サンシャインシティ内会議室(お申込みをされた方に詳細をお知らせします)
参加費:古代オリエント博物館友の会会員:500円、一般:1000円
お申込み方法:Peatixよりお申込みください。
https://20260228kish.peatix.com
※はじめてPeatixをご利用される方は、アカウントの作成が必要となります
講演内容:
キシュ(Kish)遺跡は、メソポタミア文明の形成期において卓越した地位を築いていたため、その考古学的価値ははかりしれません。かつての英米・仏の調査の見直しおよび、新たな発掘がはじまろうとしています。(講師・記)
2026年3月6日開催:セミナー「イラン考古学最前線(2026)」
セミナーの案内をいただきましたので、お知らせします。
*********************************
セミナー「イラン考古学最前線(2026)」
日程:3月6日(金)15:00~17:30
開催趣旨:
このたび、イラン・イスラム共和国より、ホセイン・アジジ・ハラナギ博士(イラン考古学研究センター)をお招きし、研究会「イラン考古学最前線(2026)」を開催することになりました。
ホセイン博士が、昨年6月に発見したパルティア時代の大規模墓地に関して発表を行うほか、日本の中堅・若手研究者が、近年の研究成果を報告いたします。
皆さまのご参加をお待ちしております。
主催:
東京文化財研究所文化遺産国際協力センター保存計画研究室
日本学術振興会科学研究費(基盤研究A)「ディルムン文明形成に関する考古学的研究」
協力:
日本学術振興会科学研究費(特別推進研究)「サピエンス数理先史学ー新人拡散にともなう文化進化モデリング」
会場:東京文化財研究所4階新会議室
(https://www.tobunken.go.jp/japanese/navi/map.html)
申し込み先:安倍雅史(東京文化財研究所文化遺産国際協力センター保存計画研究室)abe-m6e@nich.go.jp
プログラム:
15:00~15:30:Hossein Azizi Kharanaghi
「Gur-e Kafaran, a Newly Discovered Historical Site in Yazd, Middle Iran」
15:30~16:00:Yui ARIMATSU
「Beginning of the Bronze Age Burnished Gray Ware in Northeastern Iran」
16:00~16:15:Tea Break
16:15~16:45:Takehiro MIKI
「The Final Phase of the Jari: A Study of Neolithic Pottery from Tall-e Jari B, Fars, Iran」
16:45~17:15:Shizuka MIYAI
「Lithic Industry from the Shamsabad Period to the Middle Bakun Period in Southwestern Iran: Insights from Tall-e Jari A and Tall-e Gap」
17:15~17:30:General Discussion
2025年10月25日~2026年3月31日開催:企画展「シリアの伝統工芸」
展覧会の案内をいただきましたのでお知らせします。
*********************************
シリアの伝統工芸にかんする企画展を開催いたします。ぜひお越しください。
https://teikyo.jp/museum/exhibition/2025-other-syria/
——————————————-
企画展「シリアの伝統工芸」
2025.10.25~2026.3.31
帝京大学総合博物館 常設展示室 入場無料
(高幡不動/聖蹟桜ヶ丘/多摩センターからバス)
休館日:日祝、入試日
特別開館:10月26日(日)(青舎祭)
——————————————-
*本企画展は、帝京大学やまなし伝統工芸館で開催した企画展(2025年5~8月)の巡回展です。
2026年3月19日開催研究会:The Mesopotamian Exorcist: Ritual Healer, Scholar, and Divine Messenger
研究会の案内をいただきましたので、お知らせします。
(追記:日程が3月4日から3月19日に変更になったとのことです)
*********************************
筑波大学西アジア文明研究センターにおいて、第15回定例研究会を下記の通りハイブリッド方式で開催いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
【西アジア文明研究センター第15回定例研究会】
演者:Evelyne Koubkova(筑波大学 人文社会系)
演題:The Mesopotamian Exorcist: Ritual Healer, Scholar, and Divine Messenger
日時:2026年3月4日→19日 17:00~19:00
会場:西アジア文明研究センターとZoomミーティングのハイブリット
【対面】筑波大学西アジア文明研究センター(筑波大学つくばキャンパス共同研究棟A601、https://rcwac.histanth.tsukuba.ac.jp/access)
【オンライン】Zoom ミーティング
URL: https://us02web.zoom.us/j/84805741862?pwd=dyaFndPs7wfydjBaWHRPMoZKJyBQbm.1
ミーティング ID: 848 0574 1862
パスコード: 806850
※英語発表(Zoomの翻訳機能による日本語字幕有)
下記のウェブサイトにも掲載しています。
https://rcwac.histanth.tsukuba.ac.jp/events/event/lecture-koubkova
筑波大学西アジア文明研究センター
https://rcwac.histanth.tsukuba.ac.jp
===
バーレーンで行っている発掘調査の動画
西藤清秀会員よりバーレーンで行っている発掘調査の動画をご紹介いただきましたので、お知らせします。
*********************************
現在、バーレーンで調査を行っていますが、在バーレーン日本大使館が我々の調査の一部(未盗掘墓の天井石を外す作業)を紹介してくれています。
ご関心のある方は、ぜひご覧ください。
https://www.instagram.com/reel/DUBLRwMDOVW/?igsh=MTl2ZGVnaG5hZWpxdQ==
西藤 清秀
2026年1月28日開催講演会:From Hellenistic To Medieval: Detection Of Alexandria Hydrological Landscapes And Water Utilities
講演会の案内をいただきましたので、お知らせします。
*********************************
筑波大学西アジア文明研究センターにおいて、講演会を下記の通りハイブリッド方式で開催いたします。
皆様のご参加をお待ちしております。
【From Hellenistic To Medieval: Detection Of Alexandria Hydrological Landscapes And Water Utilities】
〈講師 / Speaker〉Dr. Mohamed Soliman モハメド・ソリマン博士 (武蔵野大学アジアAI研究所 / Asia AI Institute (AAII) Musashino University)
〈演題 / Title〉 From Hellenistic To Medieval: Detection Of Alexandria Hydrological Landscapes And Water Utilities
〈日時 / Date & Time〉
2026年1月28日(水) 16:45-18:15 January 28, 2026 (Wed.) 16:45-18:15 (JST)
〈会場 / Venue〉
筑波大学西アジア文明研究センター(筑波大学筑波キャンパス共同研究棟A601)およびオンライン(Zoom)
University of Tsukuba, Research Center for West Asian Civilization
(Cooperative Research Bldg. A601, Tsukuba Campus, U Tsukuba) and online (Zoom)
〇オンライン参加登録はこちら / For online participation, please register here:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl0iI7tl9069IlIz1LIpMaqElJFgVTHTr7M9d2Xk9Al_3l_g/viewform
下記のウェブサイトにも掲載しています。
https://rcwac.histanth.tsukuba.ac.jp/events/event/Soliman-lecture
筑波大学西アジア文明研究センター
https://rcwac.histanth.tsukuba.ac.jp
2026年2月9日開催講演会・12日開催研究会:Rediscovering Southern Iraq: Lost Settlements and Cities from Babylonia to the Hellenistic World;Current Issues and Future Directions in Third-Millennium Mesopotamian Studies
講演会・研究会の案内をいただきましたのでお知らせします。
*********************************
国士舘大学21世紀アジア学部附属イラク古代文化研究所では、考古学者のRobert Killick 博士とJane Moon 博士を招聘し、2026年2月9日(月)に東京で講演会、2月12日(木)京都で研究会を開催します。お時間のある方は是非ご参加ください。
【講師紹介】
Robert Killick 博士は、中東を中心に長年にわたり考古学調査と文化遺産保護に携わってきた考古学者・文化遺産コンサルタントである。北イラク3千年紀考古学を専門とし、ICCROMに6年間勤務するなど、遺跡保存・管理、パブリック・アーケオロジー、デジタル記録技術の分野で国際的に活躍してきた。これまでにイラク、バーレーン、カタール、ヨルダンで多数の発掘調査を指揮・共同指揮し、近年はTell Khaiber(第一海国時代)およびアルサケス朝の大都市、Charax Spasinouでの調査を主導した。学術出版も多く、メソポタミア考古学と湾岸地域研究の発展に大きく貢献している。
Jane Moon 博士は、中東考古学を専門とする考古学者で、1970年代より長年にわたりイラクを中心とした発掘調査と研究に携わってきた。初期王朝時代のアブ・サラービーフ遺跡での調査を皮切りに、ハムリン・ダム地域、エスキ・モスル・ダム地域など数多くの発掘に参加し、南メソポタミア考古学の発展に大きく貢献した。1990年代にはバーレーンのディルムン文化遺跡サール遺跡の共同調査主任を務め、2010年代以降はTell Khaiber(第一海国時代)およびバスラ近郊の都市Charax Spasinouの調査を共同主導した。特に土器研究と出土遺物の整理・出版に精通し、その学術的成果は国際的に高く評価されている。
*******************************************************************************
【東京会場】
■タイトル:Rediscovering Southern Iraq: Lost Settlements and Cities from Babylonia to the Hellenistic World
■日時:2026年2月9日(月)15時〜17時20分
■場所:国士舘大学世田谷キャンパス メイプルセンチュリーホール4階 中教室
(東京都世田谷区世田谷4-28-1)
■プログラム
15:00-15:05 開会の辞
15:05-16:05 Jane Moon
Light on the ‘Dark Age’ of Babylonia: a settlement of the First Sealand period, c. 1500 BC.
16:05-16:15 休憩
16:15-17:15 Robert Killick
Charax Spasinou: Mapping Alexander the Great’s city in southern Iraq.
17:15-17:20 閉会の辞
◆使用言語:英語(日本語自動翻訳あり)
◆参加費:無料
◆定員:対面30名
◆事前申込:必要、申込締め切り2026年2月4日(水)まで
下記登録フォームよりお申し込みください。【東京会場】のみの申し込みとなります。
https://forms.office.com/r/HHgpmVFSj9
定員に達ししだい締め切らせていただきます。
*******************************************
【京都会場】
■タイトル:Current Issues and Future Directions in Third-Millennium Mesopotamian Studies
■日時:2026年2月12日(木)13時〜17時
■場所:京都大学ユーラシア文化研究センター(羽田記念館)
(京都市北区大宮南田尻町13)
■プログラム
13:00-13:05 開会の辞
13:05-13:45 Robert Killick
Northern Mesopotamia in the first half of the third millennium BC: The view from Tell Mohammed Arab.
13:45-14:25 Jane Moon
A century of Sumerian ceramic studies: are we wiser now?
14:25-14:45 休憩
14:45-15:05 森 若葉 前川和也 ハイダル・オライビ・アルマモリ
Umm-al-Aqarib(Gišša)文書の概要
15:05-15:25 小泉 輝
バビロニアにおける初期王朝時代からアッカド王朝時代にかけての考古学的な編年の再考
15:25-15:45 常木麻衣
キシュ出土分銅に関する一考察
15:45-16:05 小口和美
テル・グッバにおける前3千年紀後半の再検討-土器資料に基づく考察-
16:05-16:15 休憩
16:15-16:55 ディスカッション
16:55-17:00 閉会の辞
プログラムは、当日変更となる場合があります。
◆使用言語:英語(日本語自動翻訳あり)、日本語
◆参加費:無料
◆定員:対面20名
◆事前申込:必要、申込締め切り2026年2月4日(水)まで
下記登録フォームよりお申し込みください。【京都会場】のみの申し込みとなります。
https://forms.office.com/r/mVTXdEk1G8
定員に達ししだい締め切らせていただきます。
◆主催:国士舘大学21世紀アジア学部附属イラク古代文化研究所
◆本講演会及び研究会は、JSPS科研費20K01006(研究代表者:小口和美) の研究活動の一環である。
◆お問合せ:国士舘大学21世紀アジア学部附属イラク古代文化研究所
常木 mtsuneki@kokushikan.ac.jp
2026年1月16日・21日開催:筑波大学西アジア文明研究センターエジプト学関連講演会(2件)
講演会の案内を2件いただきましたのでお知らせします。
*********************************
筑波大学西アジア文明研究センターにおいて、講演会2件を下記の通りハイブリッド方式で開催いたします。
皆様のご参加をお待ちしております。
【THE SCRIBE’S SWIFT HAND: Unlocking History Through Hieratic Palaeography】
〈講師 / Speaker〉
Dr. Faten Kamal ファーテン・カマール博士(カイロ・エジプト博物館 Egyptian Museum in Cairo)
〈演題 / Title〉
THE SCRIBE’S SWIFT HAND: Unlocking History Through Hieratic Palaeography
〈日時 / Date & Time〉
2026年1月16日(金) 16:00-17:30 January 16, 2026 (Fri.) 16:00-17:30 (JST)
〈会場 / Venue〉
筑波大学西アジア文明研究センター(筑波大学筑波キャンパス共同研究棟A601)およびオンライン(Zoom)
University of Tsukuba, Research Center for West Asian Civilization
(Cooperative Research Bldg. A601, Tsukuba Campus, U Tsukuba) and
online (Zoom)
〇オンライン参加登録はこちら / For online participation, please register here
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOrjcax0xIk2VC-gyQ5pHJvBiN3EBGCm2sR1qOk0Bucxlrdg/viewform
下記のウェブサイトにも掲載しています。
https://rcwac.histanth.tsukuba.ac.jp/events/event/lecture-kamal
【TUT-ANKH-MAMMON: Howard Carter and the Market for Egyptian Art, 1920-1940】
〈講師 / Speaker〉
Tom Hardwick トム・ハードウィック Tom Hardwick
(エジプト学者&学芸員 Curator & Egyptologist in UK, Egypt, US)
〈演題 / Title〉
TUT-ANKH-MAMMON: Howard Carter and the Market for Egyptian Art, 1920-1940
〈日時 / Date & Time〉
2026年1月21日(水) 16:45-18:15 January 21, 2026 (Wed.) 16:45-18:15 (JST)
〈会場 / Venue〉
筑波大学西アジア文明研究センター(筑波大学筑波キャンパス共同研究棟A601)およびオンライン(Zoom)
University of Tsukuba, Research Center for West Asian Civilization
(Cooperative Research Bldg. A601, Tsukuba Campus, U Tsukuba) and
online (Zoom)
〇オンライン参加登録はこちら / For online participation, please register here
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJwm2lNvnYyeNcegR34aD2NPV1I2EYUkcEdXS8InJ5smGdxA/viewform
下記のウェブサイトにも掲載しています。
https://rcwac.histanth.tsukuba.ac.jp/events/event/lecture-hardwick
筑波大学西アジア文明研究センター
https://rcwac.histanth.tsukuba.ac.jp
…
2026年1月26日開催公開シンポジウム:古代エジプト三千年の死者の町を掘る−エジプト、北サッカラ遺跡発掘調査報告−
シンポジウムの案内をいただきましたのでお知らせします。
*********************************
各位
公開シンポジウムを以下の概要で開催いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
公開シンポジウム
古代エジプト三千年の死者の町を掘る−エジプト、北サッカラ遺跡発掘調査報告−
日時:2026年1月25日(日)13:00〜17:00
会場:筑波大学東京キャンパス文京校舎(文京区大塚3丁目29−1134講義室)
主催:科学研究費基盤研究(A)「エジプト、サッカラ遺跡の調査による古代エジプトの埋葬文化の変容に関する総合的研究」(課題番号23H00014)
共催:筑波大学西アジア文明研究センター
お申し込み:https://forms.gle/VmTc23N9ZFUyvS3T9
お問い合わせ:northsaqqara@gmail.com
プログラム
13:00 開会の挨拶
13:05〜13:40 古代エジプト三千年の墓地からのメッセージー北サッカラ遺跡発掘調査成果の概要—
河合望(筑波大学教授)
13:40〜14:00 エジプト初期文明・死者の町の原風景ー第2〜3王朝の墓の調査成果ー
竹野内恵太(早稲田大学非常勤講師)
14:00〜14:20 たかが封鎖石、されど封鎖石−発掘された2基の岩窟遺構から−
柏木裕之(東日本国際大学客員教授)
14:20〜14:35 休憩
14:35〜14:55 古代エジプトの黄金期を支えた民衆の墓地ー新王国時代の土坑墓調査報告ー
進藤瑞生(金沢大学大学院博士後期課程)
14:55〜15:15 グレコ・ローマン時代のカタコンベのギリシア語墓碑を読む
高橋亮介(東京都立大学教授)
15:15〜15:35 手のひらサイズのライフヒストリー ーグレコ・ローマン時代のカタコンベから発見された女神像からー
岡部睦(金沢大学大学院博士後期課程)
15:35〜15:55 X線分析から明らかになる北サッカラ遺跡の人間活動
阿部善也(東京電機大学助教)・村串まどか(明治大学助教)
15:55〜16:10 休憩
16:10〜16:30 遺体が語る古代エジプトの謎ー北サッカラ遺跡から出土した人骨・ミイラについてー
坂上和弘(国立科学博物館人類史研究グループ長)・馬場悠男(国立科学博物館名誉研究員)
16:30〜17:00 質疑応答・討議
2025年10月27日開催講演会:EAST MEETS WEST – AND BACK AGAIN: The Journeys of A. H. Sayce to Japan
講演会の案内をいただきましたのでお知らせします。
*********************************
筑波大学西アジア文明研究センターにおいて、講演会を下記の通りハイブリッド方式で開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。
西アジア文明研究センター講演会 / Univ. Tsukuba RCWAC Lectures
EAST MEETS WEST – AND BACK AGAIN: The Journeys of A. H. Sayce to Japan
〈講師 / Speaker〉 Dr. Thomas L. Gertzen (Berlin / Göttingen)/
トーマス・L・ゲルツェン博士(ベルリン/ゲッティンゲン)
〈演題 / Title〉 EAST MEETS WEST – AND BACK AGAIN: The Journeys of A. H. Sayce to Japan
〈日時 / Date & Time〉 2025年10月27日(月)16:45-18:00 / October 27, 2025 (Mon.) 16:45-18:00
〈会場 / Venue〉 筑波大学西アジア文明研究センター(筑波大学筑波キャンパス共同研究棟A601)およびオンライン(Zoom)/
University of Tsukuba, Research Center for West Asian Civilization (Cooperative Research Bldg. A601, Tsukuba Campus, U Tsukuba) and online
(Zoom)
〈参加登録 / Registration〉 オンライン参加登録はこちら / For online participation, please register here
https://forms.gle/moLYewbDmdc4QGiL8
下記のウェブサイトにも掲載しています。
https://rcwac.histanth.tsukuba.ac.jp/events/event/lecture1
筑波大学西アジア文明研究センター
https://rcwac.histanth.tsukuba.ac.jp
2025年11月1日開催:鶴見大学文化財学会 2025年度秋季シンポジウム「古代文明の考古学—文明社会の歴史的意義を考える—」
シンポジウムの案内をいただきましたのでお知らせします。
*********************************
鶴見大学文化財学会では、下記の要領でシンポジウムを開催いたします。
みなさま奮ってご参加ください。
鶴見大学文化財学会 2025年度秋季シンポジウム
古代文明の考古学—文明社会の歴史的意義を考える—
趣旨:このシンポジウムでは、東アジア、南アジア、西アジアの3つの地域を取り上げ、古代文明の形成過程について考えます。「文明」とは都市をもつ高度に複雑化した社会を意味していますが、世界各地でその形成過程は異なっています。その一方で、各地・各時代で共通する特質もあり、異なる地域に展開した文明社会を比較することで、人類史における「文明」の意味をより多面的に理解することができるでしょう。本シンポジウムでは、都市、文字、資源、人・モノの移動、交流といった視点から、3つの地域の古代文明社会を比較し、「古代文明」とは何か、その歴史的意義について考えてみたいと思います。
日時:2025年11月1日(土) 13:30〜16:30
会場:鶴見大学記念ホール
https://t.pia.jp/pia/venue/venue.do?venueCd=UV52
参加費:無料
発表者・論題
趣旨説明 13:30〜13:40
講演1 13:40〜14:20 東アジアにおける文明の多様性
中村大介(埼玉大学大学院人文社会科学研究科教授)
講演2 14:25〜15:05 メソポタミア文明の形成と地域間交流
下釜和也(千葉工業大学地球学研究センター研究員)
講演3 15:10〜15:50 南アジア古代文明のダイナミズム
上杉彰紀(鶴見大学文学部文化財学科教授)
総合討論 16:00〜16:30
司会:田中和彦(鶴見大学文学部文化財学科教授)
※シンポジウムのあとに、ささやかな懇親会を開催いたします。参加ご希望の方は10月20日までにuesugi-a@tsurumi-u.ac.jpまでご連絡ください。懇親会参加費は一般4000円、学生3000円です。
2025年11月15日・16日開催:令和7年度海外調査のための3次元計測実習
「海外調査のための3次元計測実習」の案内をいただきましたのでお知らせします。
*********************************
令和7年度海外調査のための3次元計測実習
開催趣旨
近年、文化遺産の世界では、Agisoft社のMetashapeやiPhoneのScaniverseなどを用いた3次元計測が急速に普及しています。
これらの技術の導入によって、作業時間が大幅に短縮されただけではなく、これまでと比べようのない高精度で文化遺産のドキュメンテーションが可能になってきています。
今年度も、日本における3次元計測の第1人者である野口淳先生を講師にお招きし、海外で文化遺産保護に携わる日本の専門家を対象に、「海外調査のための3次元計測実習」を開催いたします。
受講者の方には、2日間の実習において、Metashapeを用いた3次元計測の技術やCloud Compareの利用方法を習得していただきます。また、2日目には、Artec3D Japan社によるArtec各種3Dスキャナーのデモも行う予定です。
主催:東京文化財研究所文化遺産国際協力センター
講師:野口淳(公立小松大学次世代考古学研究センター・特任准教授)
対象:海外で文化遺産保護に携わる日本の専門家(おもに考古学、建築、保存修復、保存科学、無形文化財を専門とするもの。研究者、大学院生、学部生などが対象)
人数:20名(申し込み順)
参加費:無料
申し込み先:東京文化財研究所 安倍雅史 abe-m6e@nich.go.jp
会場:東京文化財研究所地下一階会議室
日程:2025年11月15日(土)、16日(日)
講義内容
11月15日(土)
10:00~12:00 Metashapeを利用した遺物(博物館資料)の3次元計測実習(野口先生)
12:30~14:00 昼休み
14:00~16:30 Metashapeを利用した遺物(博物館資料)の3次元計測実習(野口先生)
11月16日(日)
10:00~12:30 Metashapeを利用した遺物(博物館資料)の3次元計測実習、
Cloud Compare実習(野口先生)
12:30~14:00 昼休み
14:00~15:00 Cloud Compare実習(野口先生)
15:00~15:30 ホンジュラスにおける3次元計測の活用(ホンジュラス専門家)
15:30~16:30 Artec3D Japan社によるArtec各種3Dスキャナーのデモ