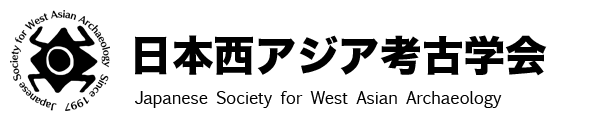展覧会のお知らせ
横浜ユーラシア文化館より、展示会のお知らせをいただきました。
詳しくは館のホームページをご覧ください。
http://www.eurasia.city.yokohama.jp/
企画展 ユーラシア 筆の軌跡 ―江上コレクションを中心に―
Traces of the Brush: From the Egami Collection with Recent Additions
当館所蔵の江上コレクションから東西の「筆」が遺した様々なかたちを展示。新しく加えられた資料も初公開します。
【会期】 2015年10月3日(土)~10月25日(日)
【会場】 横浜ユーラシア文化館 3階企画展示室(一部)
【観覧料】 一般200円、小・中学生100円
■ギャラリートーク
担当学芸員による展示解説
2015年10/11(日) 、10/25(日)各日14:00から1時間程度
【参加費】企画展観覧料のみ
■企画展「ユーラシア 筆の軌跡」関連作品展
Eurasian Art Craft展 by choko nakazono
ユーラシアのさまざまな文様にインスパイアされたオリジナル文様。自ら染めた和紙。独自のカッティング技法。この3つが織りなす中ぞの蝶子氏の作品世界をお楽しみください。
【会期】 2015年10月3日(土)~10月25日(日)
【会場】 1階旧第1玄関
【観覧料】 無料
10月17日(土)15:30から中ぞの氏による作品解説があります。参加無料。
イラン考古学セミナーのご案内(2015.9.21)
第15回 イラン考古学セミナー(2015年)のご案内
謹啓
時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
これまでに日本の調査隊がイランで行った考古学調査やその後の関連研究成果を紹介する目的で、下記セミナーを開催致します。イラン・イスラム共和国大使館(東京都
港区麻布)のご協力を得て、大使館セミナー・ルームを当日会場と致します。なお例年同様、大使館のご厚意により、当日の昼食としてイラン料理の馳走が大使
公邸にて振舞われる予定です。
会場等準備の都合がございますので、お早めにお申し込み下さい。
お誘い合わせのうえ、ふるってご参加下さいますようご案内申し上げます。
敬具
記
日時:2015年10月31日(土曜日) 10:00~14:50
場所:イラン・イスラム共和国大使館(地下鉄日比谷線広尾駅下車 徒歩15分あるいは
地下鉄南北線・都営三田線白金高輪駅より徒歩10分)
東京都港区南麻布3-13-9 / 電話 03-3446-8011
http://jp.tokyo.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=392&pageid=24402
主催:イラン・イスラム共和国大使館、筑紫女学園大学
共催:金沢大学国際文化資源学研究センター
参加費:無料
プログラム
10:00~10:10 開会の辞
Reza NAZAR AHARI, Ph. D(イラン・イスラム共和国大使閣下)
10:10~11:10 「近年の発掘調査から見たイランにおける農耕・牧畜の起源」
(The Origins of Agriculture in Iran:the Recent Excavations and
Archaeological Studies in Iran)」
安倍 雅史(早稲田大学高等研究所)
11:10~12:10
「シルクロードを旅してきたガラス器 ―化学組成による起源推定―
(Glass vessels Travelled the Silk Road: Provenance Investigation based on Chemical Composition)」
阿部 善也(東京理科大学)
12:10~12:20 食事会場への移動
12:20~13:30 昼食会
13:30~13:40 発表会場への移動
13:40~14:40 「イラン古代の建築術-メソポタミアとの比較の視点から(Iranian Ancient Architecture: from a Comparison with the Mesopotamian Architecture)」
岡田 保良(国士舘大学)
14:40~14:50 閉会の辞 大津 忠彦(筑紫女学園大学)
お申し込み・お問合せ先:
金沢大学歴史言語文化学系 足立拓朗
〒920-1192 金沢市角間町 金沢大学 歴史言語文化学系
電話 076-264-5328
FAX 076-264-5362
e-mail: mppnb@yahoo.co.jp
できるだけ、e-mailかファックスでお申し込みください。
シンポジウムのご案内(2015.9.2)
シンポジウム「イスラームと文化遺産—文化的多様性の維持と多文化共生社会をめざして」
日時:2015年10月4日(日)9:30〜16:30(9:00開場)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス9号館5階第1会議室
主催:早稲田大学高等研究所
共催:NPO法人南アジア文化遺産センター、東北大学学際科学フロンティア研究所、新泉社
開催趣旨
2001年のターリバーンによるバーミヤーン大仏の破壊、今年に入り立て続くIS(自称『イスラム国』)による世界遺産ハトラ遺跡やパルミラ遺跡の破壊など、紛争や騒乱下において、貴重な文化遺産が意図的に破壊され続けている。
実行者は、その行為をイスラームの教義にもとづくものとして正当化しようとしている。果たして、イスラームは文化遺産を破壊するのか?
本シンポジウムでは、 まず、アフガニスタン紛争やシリア内戦など紛争や騒乱下において起きた文化遺産オ被災状況に関し報告を行い、そこから見えてくる課題について議論を行う。
また、イスラーム圏諸国で文化遺産の調査や保護に従事する研究者の報告を通じて、イスラーム諸国では、むしろ長年、積極的に自国の文化遺産保護が進められてきたという事実を一般に周知する。
その上で、考古学、文化遺産学だけではなく、文化遺産とそれを取り巻く現代社会の関係、そこにおける諸課題を掘り下げ、地域社会と連携する文化遺産の保護と莉活用への展望を議論する。
なお本シンポジウムは、2015年10月1日刊行予定の『イスラームと「文化財問題」(仮題)』(野口淳・安倍雅史編、新泉社刊)の出版と連動するものである。
プログラム
9:30 開会あいさつ 野口淳(NPO法人南アジア文化遺産センター)
9:40 基調講演『バーミヤーン大仏の破壊と復興』 前田耕作(和光大学名誉教授)
10:30 基調報告1『イスラームと文化遺産—現状の概略』野口淳(NPO法人南アジア文化遺産センター)
10:55 基調報告2『シリア―内戦下における文化財の破壊』
安倍雅史(早稲田大学高等研究所助教)、間舎裕生(東京文化財研究所客員研究員)
11:20 基調報告3『近代化政策、ナショナリズムとアナトリア諸文明—トルコにおける文化財保護』
田中英資(福岡女学院大学人文学部准教授)
11:45 基調報告4『イラン―イスラーム国家の考古学文化財保護と博物館』
有松唯(東北大学学際科学フロンティア研究所助教)
12:10 昼食休憩
【パネルディスカッション(司会:野口淳)】
13:20 セッション1『紛争・騒乱下における文化遺産』
パネラー:河合望(早稲田大学高等研究所准教授)、安倍雅史、間舎裕生、田中英資
14:35 休憩
14:45 セッション2『地域コミュニティと文化遺産』
パネラー:山泰幸(関西学院大学人間福祉学部教授)、前島訓子(名古屋大学大学院環境学研究科研究員)、有松唯、田中英資
16:00 閉会挨拶 前田耕作
なお本シンポジウムは、(公財)三菱UFJ国際財団2015年度助成金による国際交流事業『文化遺産をめぐる対話』の一部を構成します。
問い合わせ先
安倍雅史(早稲田大学高等研究所)abemasashi@aoni.waseda.jp
野口淳(NPO法人南アジア文化遺産センター)fujimicho0@hotmail.com
早稲田大学高等研究所 http://www.waseda.jp/event/symposium/sym_151004.html
南アジア文化財センター https://sites.google.com/site/jcsachweb/
写真集『ARAB』ご希望の方へのご連絡
当会が進めております「シリア文化財救済支援」事業に関しましては、ご理解ご協力賜り誠にありがとうございます。ご寄付いただく方も増えてきており、篤く御礼申し上げます。
このうち、三井住友銀行の口座にご寄付をいただいた方はカタカナ名しか把握出来ませんので、1万円以上のご寄付で、吉竹めぐみ氏よりご提供のあった写真集をご入用の方は、当学会事務局宛ににメールかファックスにて、ご氏名・送付先をお知らせ下さい。
e-mail: office@jswaa.org
FAX: 029-853-4432
講演会のお知らせ(2015.7.2)
NPO法人南アジア文化遺産センター・NPO法人WAC Japan講演会
2016年世界考古学会議京都大会関連企画
インド北西部乾燥地域における農耕・牧畜の開始-完新世の環境変化、資源開発と景観-
Emergence of Agriculture and Pastoralism in the arid northwestern India: environmental change, resouce exploitation and landscape
日本で開催される第19回国際第四紀学連合大会にあわせて来日されるマデラ先生をお招きし、下記のとおり講演会を開催しますので、みなさん、ふるってご参加ください。
●講演者:Prof. Dr. Marco Madella(スペイン・カタルーニャ先端学術研究所研究教授/ポンペウ・ファブラ大学人文学部)
専門は、考古植物学・環境考古学。植物資源の開発利用と食糧生産の社会生態学的ダイナミクスを研究テーマとして、過去の社会と環境の相互作用研究(SimulPast-CONSOLIDER)、ブラジルの森林生態系の社会生態学的ダイナミクス研究プロジェクト、トルコ・チャタルヒュユック遺跡調査(考古植物学チーム主任)などに参画する。
当日は、自身が主宰するインド北西部グジャラート州考古学プロジェクト(NoGAP)を中心に、最新の研究成果をご紹介して頂きます。
プロフィール:http://www.upf.edu/huma/es/directori/alfabetic/madella.html
●とき:2015年 8月3日(月)18:30~20:30
●場所:同志社大学室町キャンパス寒梅館地下A会議室 ※京都市営地下鉄今出川駅北へ徒歩1分(下記地図参照)
●主催:NPO法人南アジア文化遺産センターNPO法人WAC Japan
共催:大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所
●資料代:¥300
●講演後、ささやかな懇親会をします。
●問い合わせ先
若林邦彦(WAC Japan事務局): wac8kyoto@gmail.com
野口 淳(南アジア文化遺産センター事務局): npo.jcsach@gmail.com
ホームページリニューアル(2015.7.1)
学会ホームページをリニューアル公開しました。
イラン考古学セミナーの予告(2015.6.24)
第15回 イラン考古学セミナー(2015年)のご案内
例年開催しておりますイラン大使館での「イラン考古学セミナー」をご案内いたします。 今年は秋開催となります。くわしくは下記をご覧ください。 例年とは異なり、秋季開催(10/31頃)となりますので、ご注意ください。 9月末に改めてご連絡いたします。参加お申し込みはそれまでどうぞお待ち下さい。
金沢大学 足立拓朗
第15回 イラン考古学セミナー(2015年)のご案内
謹啓
時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
これまでに日本の調査隊がイランで行った考古学調査やその後の関連研究成果を紹介する目的で、下記セミナーを本年秋に開催致します。イラン・イスラム共和国大使館(東京都港区麻布)のご協力を得て、大使館セミナー・ルームを当日会場と致します。なお例年同様、大使館のご厚意により、当日の昼食としてイラン料理の馳走が大使公邸にて振舞われる予定です。 会場等準備の都合がございますので、お早めにお申し込み下さい。 お誘い合わせのうえ、ふるってご参加下さいますようご案内申し上げます。
敬具
記(予定)
日時:(予定)2015年10月31日(土曜日) 10:00~14:50
場所:イラン・イスラム共和国大使館
東京都港区南麻布3-13-9 /電話 03-3446-8011
(地下鉄日比谷線広尾駅下車 徒歩15分、あるいは地下鉄南北線・都営三田線白金高輪駅より徒歩10分)
主催:イラン・イスラム共和国大使館
共催:金沢大学国際文化資源学研究センター
参加費:無料
プログラム
10:00~10:10 開会の辞 Reza NAZAR AHARI, Ph. D (イラン・イスラム共和国大使閣下)
10:10~11:10 「近年の発掘調査から見たイランにおける農耕・牧畜の起源」
(The Origins of Agriculture in Iran:the Recent Excavations and Archaeological Studies in Iran)」 安倍 雅史(早稲田大学高等研究所)
11:10~12:10 「シルクロードを旅してきたガラス器 ―化学組成による起源推定―
(Glass vessels Travelled the Silk Road: Provenance Investigation based on Chemical Composition)」 阿部 善也(東京理科大学)
12:10~12:20 食事会場への移動
12:20~13:30 昼食会
13:30~13:40 発表会場への移動
13:40~14:40 「イラン古代の建築術-メソポタミアとの比較の視点から
(Iranian Ancient Architecture: from a Comparison with the Mesopotamian Architecture)」 岡田 保良(国士舘大学)
14:40~14:50 閉会の辞 大津 忠彦(筑紫女学園大学)
お申し込み・お問合せ先:(お申し込みは9月末以降にお願いします)
金沢大学歴史言語文化学系 足立拓朗
〒920-1192 金沢市角間町 金沢大学 歴史言語文化学系 電話 076-264-5328 FAX 076-264-5362
e-mail: mppnb@yahoo.co.jp
できるだけ、e-mailかファックスでお申し込みください。
講演会のお知らせ(2015.6.23)
イコモスパートナーシップによる (株)ANAセールスとの共同企画「イコモスアカデミー」開催のご案内
【テーマ】「シルクロードの古跡を巡る」
【講 師】前田耕作氏 (日本イコモス国内委員会副委員長)
【日 時】2015年7月16日(木) 14:00~15:30
【場 所】ANAワンダーラウンジ(東京都中央区日本橋2-14-1 フロントプレイス日本橋1階)
【URL】 https://www.ana.co.jp/inttour/wonderlounge/ ※HP下方に会場の地図があります。
イコモスアカデミーは、毎月1回、世界の様々な地域や文化をテーマとして、日本イコモス専門家が、なかなか聞くことができない専門的な話を、一般の方々にも分かりやすく紹介しています。
会員以外の方でも無料で参加できますので、お誘いあわせの上、奮ってご参加ください。
参加ご希望の方は、以下へお電話でお申込みをお願いいたします。
ANAセールス 0570-070-860 ※受付時間 9:30~18:00
(IP電話からはこちらへおかけください。 092-720-8356)
シンポジウムのご案内(2015.6.17)
第4回太陽の船シンポジウム~「今!太陽の船プロジェクトは・・・」~
日時:2015年7月13日(月) 18:00開場 18:30~20:30(開場18:00)
場所:早稲田大学小野記念講堂
プログラム:
18:00 開場
【第1部】
18:30 開会の挨拶 近藤二郎(早稲田大学教授・早稲田大学エジプト学研究所所長)
18:35 太陽の船復原プロジェクトとは 吉村作治(東日本国際大学学長・NPO法人太陽の船復原研究所所長)
18:45 太陽の船復原プロジェクトの現状 黒河内宏昌(NPO法人太陽の船復原研究所教授)
18:55 エジプト文化遺産分野へのJICA支援 森裕之(独立行政法人国際協力機構(JICA) 中東・欧州部次長)
休憩
【第2部】
19:20 現場からの報告(1)ピットの中はこうなっている 高橋寿光(東日本国際大学客員助教)
19:35 現場からの報告(2)太陽の船にはこんな材料が使われていた 西坂朗子(東日本国際大学客員准教授)
19:50 現場からの報告(3)太陽の船復元考察が始まった 柏木裕之(東日本国際大学客員教授)
20:05 総括 吉村作治
20:30 閉会
司会:河合 望(早稲田大学准教授)
主催:早稲田大学エジプト学研究所、東日本国際大学エジプト考古学研究所、日本エジプト学会、NPO法人太陽の船復原研究所
後援:早稲田大学総合研究機構
協賛:独立行政法人国際協力機構(JICA)、株式会社ニトリホールディングス
協力:東京大学生産技術研究所大石武史研究室、女子美術大学内山博子研究室、株式会社アケト
【お申し込み方法】
1.氏名
2.メールアドレスまたは返信可能なFAX番号
3.住所
4.電話番号
をご記入の上お申し込みください。複数人登録される方は全員のお名前をお知らせください。入場整理券を送付いたします。
当日は、入場整理券をプリントアウトしてお持ちください。定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。
申し込みメールアドレス:waseda.egypt@gmail.com
申し込みFAX番号:03-5285-1302
参加申込み締切日:2015年7月6日(月)
HP:http://www.egyptpro.sci.waseda.ac.jp/event.html#solarboat4th
講演会のご案内(2015.6.12)
ブルガリア考古学連続講演会
このたび、国際文化研究所の招きにより、ブルガリア科学アカデミー上級研究員のディアナ・ゲルゴヴァ教授が来日し、ブルガリア北東部ズボリャノヴォ地区のトラキア人古墳(紀元前4~3世紀)における発掘調査での新発見について、大阪、岡山、東京の三会場で連続講演を行います。 皆様の積極的なご参加をお待ちしております。
大阪会場:大阪府立弥生文化博物館 (http://www.kanku-city.or.jp/yayoi/index.html)
日時:6月19日(金) 13:00~15:30
会場:大阪府立弥生文化博物館1階ホール
基調報告:田尾誠敏(東海大学非常勤講師)
講演:「ブルガリア、文明の十字路を掘る」
講師:ディアナ・ゲルゴヴァ、日本語通訳あり
定員170名、事前申し込み不要、聴講無料(ただし入館料別途)
http://www.kanku-city.or.jp/yayoi/lecturer/index_back.html
岡山会場:岡山市立オリエント美術館(http://www.orientmuseum.jp/)
日時:6月20日(土) 14:00~16:00
会場:岡山市立オリエント美術館地下講堂
講演:「トラキア黄金文明の聖地ズボリャノヴォの新発見ーブルガリア考古学の最新情報ー」
講師:ディアナ・ゲルゴヴァ(日本語通訳あり)
聴講料:500円(友の会会員は300円)、要申込
問合せ・申込み 岡山市立オリエント美術館 TEL 086-232-3636 orient@city.okayama.jp
http://www.orientmuseum.jp/page01.php#num2
東京会場:古代オリエント博物館(http://aom-tokyo.com/)
日時:6月21日(日) 13:30~15:00
会場:池袋サンシャインシティ文化会館7階会議室704・705室
講演「ズボリャノヴォ(ブルガリア)における考古学の新発見ー黄金のトラキア文明を掘るー」
講師:ディアナ・ゲルゴヴァ(日本語通訳あり)
聴講料:500円(友の会会員は無料)、事前申し込み不要
http://aom-tokyo.com/event/150621.html
講演会のご案内(2015.5.27)
一般講演会「パキスタン北部地方に『法顕の道』を訪ねて(仮)」
講師:土谷遥子氏(元・上智大学教授)
日時:2015年6月27日(土)13:00開場、13:30開演、16:30閉会予定
主催:インド考古研究会・NPO法人南アジア文化遺産センター・公益財団法人日本パキスタン協会
参加申込:http://kokucheese.com/event/index/301007/
申込期限:6/22 23:59
※会場席数には限りがありますので、事前申し込みいただいた方を優先とさせていただきます。
資料代:¥1,000(主催3団体の会員 500)
パキスタン北部地域における文化遺産と『法顕の道』について、長年にわたり単身で現地調査を重ねてきた土谷遥子先生(元・上智大学教授)により、多数の写真スライドとともにお話しいただきます。
三蔵法師の名で有名な玄奘より200年以上前に中国からインドへ求法の旅に出た法顕の足跡、『法顕伝』の記述を手がかりに、パキスタン北部の山岳地帯に分け入ってその足跡を見つけ出した探検調査旅行の記録を、貴重な写真とともにお送りいたします。
公開講座のご案内(2015.5.8)
平成27年度 大正大学綜合仏教研究所特別講座
テーマ 文献と考古学から観たガンダーラの佛教
講師 桑山 正進 先生(綜合仏教研究所特別講師・京都大学名誉教授)
本研究所では特別講座の先生をお迎えし、下記の日程で講義を開催いたします。どなたでも聴講できますので、ふるってご参加ください(聴講無料・予約不要です)。 ※定員に達した場合は締め切らせていただくことがあります。
[時間] 14:50~16:20(本学4時限目)
[場所] 大正大学綜合仏教研究所 研究室1(3号館4階) 大正大学巣鴨キャンパス
都営三田線 「西巣鴨」駅下車すぐ 都営荒川線 「庚申塚」駅下車、徒歩5分
【講義概要】
仏教がインド外へ出ることについては、玄関先であるガンダーラ地方で化粧直しをしたことがとても重要です。ガンダーラはインド内部の精神とほとんど対極にありました。この東アジア仏教の策源地の特異性を考古学と文献から縦横に考察します。ガンダーラは石や石膏の仏像で有名ですが、本講はいわゆる美術史のはなしではないことをお断りしておきます。
第1回目 5月20日(水) 地理上のガンダーラとその歴史
第2回目 6月17日(水) 宇宙軸信仰とストゥーパの生成
第3回目 7月1日(水) ガンダーラにおけるストゥーパの変貌
第4回目 7月15日(水) インドの無仏像とガンダーラの仏像
第5回目 10月14日(水) 聖遺物と聖跡の創作
第6回目 11月28日(水) 仏鉢の所在
第7回目 11月18日(水) 行歴僧の旅程
第8回目 12月9日(水) ガンダーラの凋落
第9回目 1月6日(水) 中国における末法思想
第10回目 1月27日(水) ナレーンドラヤシャス、ジナグプタ、玄奘
【問い合わせ先】 大正大学綜合仏教研究所 03-3918-7311(代表)
http://www.tais.ac.jp/related/labo/sobutsu/sobutsu.html
※日程等に変更が生じた場合は、随時、上記HP上にてご案内いたします。