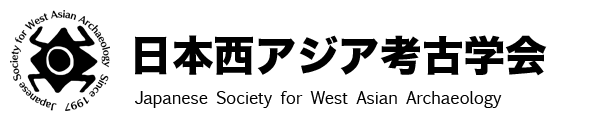2022年12月22日開催:「 人・モノ・自然プロジェクトキックオフシンポジウム」
シンポジウムの案内をいただきましたのでお知らせします。
当会の分野とは関連が薄いものですが、隣接分野としてご興味があればご参加ください。
***********************************
「 人・モノ・自然プロジェクトキックオフシンポジウム」開催について
人間文化研究機構では、「人新世に至る、モノを通した自然と人間の相互作用に関する研究(略称:人・モノ・自然プロジェクト)」を2022年度~2027年度でおこなっております。
本プロジェクトでは、文系・理系の枠を超えた研究協力体制により、人類の資源利用などに関する研究をおこなっていく予定にしています。
基本計画はこちら
https://www.nihu.jp/sites/default/files/research/MasterPlan_4thMultidisciplinaryCollaborative_02.pdf?fbclid=IwAR2j2s-vgtSQTSyOXlnrzjyV4dDpuTdJFhv3a0afFMphJDSsG9xnvCh4438
つきましては、本プロジェクトのキックオフシンポジウムを2022年12月22日(木)に開催することになりました。
https://www.chikyu.ac.jp/rihn/events/detail/46/
本キックオフシンポジウムは、第12回同位体環境学シンポジウムの基調講演(大河内博士)と合同で行います。
【開催日時】
2022年12月22日(木)13:00~17:00 開催方式:オンライン(zoom meeting)
【プログラム】
13:00-13:05 山極所長あいさつ
<同位体研究の最先端>(日本学士院エジンバラ公賞受賞記念公演)
13:05-13:50 大河内直彦(海洋研究開発機構)「同位体生態学 ver. 2.1」
<プロジェクト計画とお誘い>
14:00-14:25 陀安一郎「人・モノ・自然プロジェクトの目指すもの」
14:25-14:50 坂本稔(国立歴史民俗博物館)「同位体ではかる時間軸の高精度化」
14:50-15:20 瀧上舞(国立科学博物館)「アンデス考古学研究への応用と研究計画」
<文理の協働でわかること>
15:40-16:05 米田穣(東京大学) 「安定同位体でみた縄文ムラのヒトと動物・植物」
16:05-16:30 中塚武(名古屋大学)「気候と社会の歴史的関係から分かること」
16:30-17:00 総合討論
【申し込み方法】
聴講の申し込みは、google form(https://forms.gle/L4bNsPWC2idhZARx6)から行なってください。
締切12月16日(金)となっております。
ご質問等ございましたら、総合地球環境学研究所 研究基盤国際センター 計測・分析室(doitai@chikyu.ac.jp)までお問い合わせください。
2022年12月10日開催:Dr. José Manuel Alba Gómez講演会
講演会の案内をいただきましたのでお知らせします。
***********************************
⾦沢⼤学エジプト学特別講演会2022-3+セミナー
⾦沢⼤学古代⽂明・⽂化資源学研究所 / 新学術創成研究機構 共催
⽇時 2022年12⽉10⽇(土)13:00-17:00
場所 ⾦沢⼤学総合教育1号館3階B10教室
言語 英語(通訳なし)
講演者
Dr. José Manuel Alba Gómez
Co-director Qubbet el-Hawa Project
Universidad de Jaén
スペイン、ハエン⼤学
ホセ・マニュエル・アルバ・ゴメツ博⼠
開会 13:00
講演 13:05~14:05
From the beginnings to the present: the works of the University of Jaen at Qubbet el-Hawa (Aswan)
休憩 14:05~14:15
セミナー1 14:15〜15:15
The recontextualization of Qubbet el-Hawa through pottery
休憩15:15〜15:30
セミナー2 15:30〜16:30
The use of experimental archeology in research: the case of plant remains
ディスカッション 16:30〜17:00
閉会 17:00
連絡先:nozomu.kawai@staff.kanazawa-u.ac.jp
2022年12月13日開催オンライン研究会「西アジアにおける都市の始まりと物資管理システム」
オンライン研究会の案内をいただきましたのでお知らせします。
***********************************
新学術領域研究「都市文明の本質」におきまして、オンライン研究会が行われますので、お知らせいたします。
———————————————————————————————————————
C01-計画研究05 第30回研究会
計画研究05「中世から近代の西アジア・イスラーム都市の構造に関する歴史学的研究」による第30回研究会を開催します。
「都市とは何か」を検討するにあたり、さまざまな地域や時代の歴史をご専門とされる先生方をお招きして、オンライン(Zoom)による連続講演会「都市の世界史」を開催しております。
第8回は下記の要領で行います。
日時:2022年12月13日(火)19:30~21:00
講師:常木 晃先生(筑波大学)
テーマ:「西アジアにおける都市の始まりと物資管理システム」
【講師紹介】
筑波大学名誉教授。専門は西アジア先史考古学。特に農耕社会の形成から都市の発達までを主要なテーマとし、イラン、シリア、イラクで発掘調査を行う。編著書に、The Neolithic Cemetery at Tell el-Kerkh (Oxford: Archaeopress, 2022), The Emergence of Pottery in West Asia (Oxford: Oxbow Books, 2017), Ancient West Asian Civilization: Geoenvironment and Society in the Pre-Islamic Middle East (New York: Springer, 2016), A History of Syria in One Hundred Sites (Oxford: Archaeopress, 2016)などがある。
*西アジアでは、新石器時代からの社会の拡大と複雑化を基盤として、銅石器時代に「都市」と言えるような集落が登場します。今回は、そのプロセスを振り返り、なぜ都市が登場するのかを考えるとともに、印章や印影などの物資管理システムの発達についてお話しいただきます。
申込先: https://forms.gle/fgGGj8aBRB7NX4ae7
*Googleフォームでの申し込みとなります。前日の12月12日正午までに、上記のURLからお申し込みください。
*お申し込みいただいた方へ、前日中に、当日のURL(Zoom)をお送りいたします。
本連続講演会は、新学術領域研究「都市文明の本質:古代西アジアにおける都市の発生と変容の学際研究」計画研究「中世から近代の西アジア・イスラーム都市の構造に関する歴史学的研究」(代表:守川知子)にて行ってきた「西アジア都市研究」を発展させたものです。
ご講演は45~50分、質疑応答は35~40分と、ディスカッションを重視した時間配分となっております。
奮ってご参加くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
【これまでの講演会】
第1回・4月22日(金) 深見奈緒子先生(日本学術振興会カイロ研究連絡センター)「都市の歴史:生態圏と形態・人口」
第2回・5月24日(火) 森本公誠先生(東大寺)「アラブの軍営都市(ミスル)」
第3回・6月21日(火) 菅谷成子先生(愛媛大学)「スペイン植民地都市マニラ」
第4回・7月15日(金) 森安孝夫先生(大阪大学)「中央ユーラシアのオアシス都市と草原都市」
第5回・9月27日(水) 稲葉穣先生(京都大学)「都市と山岳フロンティア」
第6回・10月21日(金) 深沢克己先生(東京大学・日本学士院)「地中海都市の歴史像:マルセイユの事例から」
第7回・11月25日(金) 松井洋子先生(東京大学)「近世日本の貿易都市長崎」
【今後の予定】
第9回・1月17日(火) 佐川英治先生(東京大学)
第10回・3月 南川高志先生(佛教大学)
皆様のご参加をお待ちしております。
守川知子
tomomo[a]l.u-tokyo.ac.jp
https://www.l.u-tokyo.ac.jp/
——————————————————————————————————————–
皆様のご参加をお待ちしております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
西アジア文明研究センター事務室
**************************************************************************
科学研究費補助金 新学術領域研究(研究領域提案型)
「西アジア都市」事務室
〒305-8571 茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学西アジア文明研究センター
029 853 5441
rcwasia@hass.tsukuba.ac.jp
2022年12月11日開催:国際シンポジウム『考古学と国際貢献︓バーレーンの文化遺産保護に対する日本の貢献』
国際シンポジウムの案内をいただきましたのでお知らせします。
***********************************
日本・バーレーン王国外交関係樹立50 周年事業
国際シンポジウム『考古学と国際貢献︓バーレーンの文化遺産保護に対する日本の貢献』
12 月11 日(日) 13 時〜18 時
会場:東京文化財研究所地下一階セミナー室
開催趣旨
中東のバーレーンは、東京23 区と川崎市をあわせた程度の小さな島国ですが、魅力ある文化遺産を数多く有しています。
とくに今から4 千年前の青銅器時代には、バーレーンはディルムンと呼ばれ、メソポタミア、オマーン半島、そしてインダスを結ぶ海洋交易を独占し繁栄したことが知られています。この時代、バーレーンには、7 万5 千基もの古墳が作られ、19 世紀末以来、多くの考古学者を惹きつけてきました。この古墳群は、2019 年にはユネスコの世界文化遺産にも登録されています。
今回の国際シンポジウムは、日本とバーレーン王国の外交関係樹立50 周年を記念して開催するものです。バーレーンの国立博物館館長ほか、バーレーンで発掘調査を行っている各国の発掘調査団団長、日本の専門家が一堂にかいします。シンポジウムを通じて、多くの方に、バーレーンの文化遺産の魅力、また長年の日本の貢献について、知っていただければと思います。
共催:東京文化財研究所、金沢大学古代文明・文化資源学研究所
会場:東京文化財研究所地下一階セミナー室 (〒110-8713 東京都台東区上野公園13-43)
日時:12 月11 日(日)13 時 〜 18 時
言語:英語(通訳はありません)
お申し込み:下記メール宛にお申し込みください。
abe-m6e@nich.go.jp
プログラム
12:00 開場
13:00 〜 13:10 開会挨拶
13:10 〜 13:40 『バーレーンの歴史と文化遺産』
サルマン・アル・マハリ(バーレーン国立博物館)
13:40 〜 14:10 『デンマーク隊によるバーレーン調査の歴史 (1953年〜) と現在のプロジェクト』
ステファン・ラウルセン(モースゴー博物館)
14:10 〜 14:40 『フランス隊によるバーレーン考古学調査:45 年の活動 (1977 年〜 2022 年)』
ピエール・ロンバル(バーレーン文化古物局)
14:40 〜 15:10『イギリス隊によるバーレーン考古学調査:130 年の活動 古物収集から現在まで』
ティモシー・インソール(エクスター大学)
15:10 〜 15:30 休憩
15:30 〜 15:50 『日本隊による考古学調査の歴史』
山田綾乃(東京文化財研究所)
15:50 〜 16:20 『ワーディー・アッ = サイル考古学プロジェクト』
安倍雅史(東京文化財研究所)
16:20〜16:50 『ディルムン・マッピング・プロジェクト:前期ディルムン墳墓群景観の記録と分析』
上杉彰紀(金沢大学)
16:50 〜 17:20 『バルバル神殿遺跡の 3次元モデルとその保存管理の応用』
末森薫(国立民族学博物館)
17:20 〜 17:50 『ティロス期マカバ古墳群の総合的研究』
西藤清秀(奈良県立橿原考古学研究所)
17:50 〜 18:00 閉会挨拶
2022年12月14日開催シンポジウム:Bahrain Archaeology in a Broader Context
シンポジウムの案内をいただきましたのでお知らせします。
***********************************
日本・バーレーン王国外交関係樹立50周年事業
古代文明・文化資源学研究所 考古学部門 第1回シンポジウム
『バーレーン考古学をめぐって』 Bahrain Archaeology in a Broader Context
日時:2022年12月14日(水) 13:30~17:35
場所: 金沢市西町教育研修館内金沢大学サテライトプラザ 3階 集会室
https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_koho/satellite/
920-0913 金沢市西町三番丁16番地、電話:076-232-5343
主催:金沢大学古代文明・文化資源学研究所
共催:東京文化財研究所
使用言語:英語(通訳なし)
申し込み先:takuro.adachi@gmail.com
プログラム
13:30~13:35 開会挨拶
13:35~14:05 The Latest Archaeological Discoveries in Bahrain by Bahraini Team
サルマン・アル・マハリ(Salman Al Mahari, Bahraian National Museum)
14:05~14:35 Abu Saiba: A Necropolis from the Tylos Period in Bahrain (1st cent. BCE – 1st cent. CE)
ピエール・ロンバル(Pierre Lombard, Bahrain Authority for Culture and Antiquities)
14:35~15:05 The Archaeology of Christianity in Samahij, Bahrain
ティモシー・インソール(Timothy Insoll, the University of Exeter)
15:05~15:15 休憩
15:15~15:45 The Royal Cemetery of A’ali and the Emergence of the Kingdom of Dilmun
ステファン・ラウルセン(Steffen Laursen, Moesggard Museum)
15:45~16:15 Excavations at Wadi Hedaja 1: Middle Bronze Age Cairn Fields in the Bishri Mountain Range, Supposed Homeland of the Amorite
藤井純夫・足立拓朗 (Sumio Fujii and Takuro Adachi, Kanazawa University)
16:15~16:45 Bahrain and the Indus during the Early Dilmun Period: Dynamism of Maritime Interaction Network
上杉彰紀 (Akinori Uesugi, Kanazawa University)
16:45~16:55 休憩
16:55~17:25 討論会
17:25~17:30 調印式
17:30~17:35 閉会挨拶
2022年12月2日開催オンライン研究会「テル・タバンの古バビロニアと中アッシリアの遺構・遺物」
オンライン研究会の案内をいただきましたのでお知らせします。
***********************************
新学術領域研究「都市文明の本質」におきまして、オンライン研究会が行われますので、お知らせいたします。
————————————————————————–
A02-計画研究02第24回研究会
計画研究02「古代西アジアにおける都市の景観と機能」による第24回研究会を開催します。
日時:2022年12月2日(金)18:00-19:30
会場:Zoomを用いたオンライン開催
発表者:沼本 宏俊 (国士舘大学)
「テル・タバンの古バビロニアと中アッシリアの遺構・遺物」
※ オンライン参加をご希望の方は、11月28日(月)までにrcwasia[@]hass.tsukuba.ac.jp
(「西アジア都市」事務局:土日は非対応)宛てのメールでご連絡ください。
新学術ホームページ
日本語 https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city/seminar/index.html#A02-02_24
English
https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city_EN/seminar_EN/index_EN.html#A02-02_24
————————————————————————–
皆様のご参加をお待ちしております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
西アジア文明研究センター事務室
***********************************************************************
科学研究費補助金 新学術領域研究(研究領域提案型)
「西アジア都市」事務室
〒305-8571 茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学西アジア文明研究センター
029 853 5441
rcwasia@hass.tsukuba.ac.jp
2022年11月28日~12月2日開催:15th international conference of The Archaeozoology of Southwest Asia and Adjacent Areas (ASWA[AA]) Working Group
国際考古動物学会南西アジア分科会(ICAZ-ASWA)大会の案内をいただきましたので、お知らせします。
本会は、日本西アジア考古学会が後援を行っています。
参加希望の方は、各日の参加人数が限られていますので、お早めにお申し込みください。
***********************************
日本西アジア考古学会会員のみなさま
国際考古動物学会南西アジア分科会(ICAZ-ASWA)の大会を開催します。
日時 11月28日-12月2日
会場 東京文化財研究所
発表言語は英語です(通訳なし)
プログラムは以下の大会HPをご覧ください。
学会HP http://www.aswa2022.jp/index.html
ASWA 15th International Meeting – 28 November–2 December, 2022, Tokyo (Japan)
This is the website for the 15th international conference of The Archaeozoology of Southwest Asia and Adjacent Areas (ASWA[AA]) Working Group, which will be held in November 2022 in Tokyo. The ASWA was established as a working group within the International Council for Archaeozoology (ICAZ) to promote zooarchaeological research in Southwest Asia.
www.aswa2022.jp
ASWA(Archaeozoology of Southwest Asia and Adjacent Areas)は西アジアとそれに隣接する地域(東地中海、北アフリカ、コーカサス、中央アジア、南アジア)の考古遺跡から出土する動物骨を研究対象とする研究者が集う国際学会です。研究の対象となる時期は旧石器時代から中世にわたり、内容は家畜化、家畜の伝播と受容、過去の生業や社会、貝や動物製品の交易、安定同位体分析、古DNA分析など多岐にわたります。
聴講希望の方はグーグルフォーム からお申し込みください。
各日30名、先着順でうけつけます。
なお、12月1日午後につきましては、会場の都合で聴講を受けつけない可能性があります。その場合はご了承ください。
資料代(要旨集)実費として受付で1000円を申し受けます。
申し込み締め切り:定員に達し次第締め切ります。
ASWA-Tokyo 聴講申し込み
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCJoJqCoIvwsz2jWwF-reST0EQwigfkIoU8afdxzViH7Tp9w/viewform?usp=sf_link
先日配信しました国際考古動物学会南西アジア分科会大会の申し込みURLですが、システムに不具合があり、変更になったと連絡がありました。
これまでにお申込みいただいている方は確認ができているとのことですので、今後お申込みいただく方は次のURLのフォームからお申し込みください。
申し込み新フォームへのリンク
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG37C_45GxefSefqP9RKpla4qj34XgK3dRdOVUtpoTx72JAw/viewform?usp=sf_link
2022年11月25日開催オンライン研究会「近世日本の貿易都市長崎」
オンライン研究会の案内をいただきましたのでお知らせします。
***********************************
新学術領域研究「都市文明の本質」におきまして、オンライン研究会が行われますので、お知らせいたします。
————————————————————————–
新学術領域研究「西アジア都市」関係者各位
C01-計画研究05 第29回研究会
計画研究05「中世から近代の西アジア・イスラーム都市の構造に関する歴史学的研究」による第29回研究会を開催します。
「都市とは何か」を検討するにあたり、さまざまな地域や時代の歴史をご専門とされる先生方をお招きして、オンライン(Zoom)による連続講演会「都市の世界史」を開催しております。
第7回は下記の要領で行います。
日時:2022年11月25日(金)19:30〜21:00
講師:松井 洋子先生(東京大学史料編纂所)
テーマ:「近世日本の貿易都市長崎」
【講師紹介】
東京大学史料編纂所教授。専門は日本近世史、日蘭関係史。著書・論文に、『一九世紀のオランダ商館(上)(下)』(共編訳著、東京大学出版会、2021年)、『甦る「豊後切支丹史料」—バチカン図書館所蔵マレガ氏収集文書より』(共編著、勉誠出版、2020年)、「貿易都市長崎からみた近世日本の「売春社会」」(『歴史学研究』926、2014年)、「長崎出島と異国女性−「外国婦人の入国禁止」再考」(『史学雑誌』118/2、2009年)などがある。
*今回は、16世紀後半にポルトガル船の寄港地として成立し、徳川政権の対外政策のもとでシナ海交易を担う直轄貿易都市となる長崎を取り上げ、「異国人」との接触のあり方や、都市住民が管理貿易を担った独自の都市社会の構造についてお話しいただきます。
申込先: https://forms.gle/Wki3qJEN4cxXgcx19
*Googleフォームでの申し込みとなります。前日の11月24日正午までに、上記のURLからお申し込みください。
*お申し込みいただいた方へ、前日中に、当日のURL(Zoom)をお送りいたします。
本連続講演会は、新学術領域研究「都市文明の本質:古代西アジアにおける都市の発生と変容の学際研究」計画研究「中世から近代の西アジア・イスラーム都市の構造に関する歴史学的研究」(代表:守川知子)にて行ってきた「西アジア都市研究」を発展させたものです。
ご講演は45〜50分、質疑応答は35〜40分と、ディスカッションを重視した時間配分となっております。
なお、第8回の12月13日(火)には、常木晃先生にご講演いただきます。
奮ってご参加くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
【これまでの講演会】
第1回・4月22日(金) 深見奈緒子先生(日本学術振興会カイロ研究連絡センター)「都市の歴史:生態圏と形態・人口」
第2回・5月24日(火) 森本公誠先生(東大寺)「アラブの軍営都市(ミスル)」
第3回・6月21日(火) 菅谷成子先生(愛媛大学)「スペイン植民地都市マニラ」
第4回・7月15日(金) 森安孝夫先生(大阪大学)「中央ユーラシアのオアシス都市と草原都市」
第5回・9月27日(水) 稲葉穣先生(京都大学)「都市と山岳フロンティア」
第6回・10月21日(金) 深沢克己先生(東京大学・日本学士院)「地中海都市の歴史像ーマルセイユの事例から」
【今後の予定】
★第8回・12月13日(火) 常木晃先生(筑波大学)「西アジアにおける都市の始まりと物資管理システム」★
第9回・1月 佐川英治先生(東京大学)
皆様のご参加をお待ちしております。
守川知子
tomomo[a]l.u-tokyo.ac.jp
https://www.l.u-tokyo.ac.jp/
新学術ホームページ
日本語 https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city/seminar/index.html#C01-05_29
English
https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city_EN/seminar_EN/index_EN.html#C01-05_29
————————————————————————–
皆様のご参加をお待ちしております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
西アジア文明研究センター事務室
***********************************************************************
科学研究費補助金 新学術領域研究(研究領域提案型)
「西アジア都市」事務室
〒305-8571 茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学西アジア文明研究センター
029 853 5441
rcwasia@hass.tsukuba.ac.jp
2022年11月13日開催公開シンポジウム「深掘り! オマーン・スルタン国」
公開シンポジウムの案内をいただきましたので、お知らせします。
対面・オンラインのハイブリッド方式での開催です。
***********************************
東京大学中東地域研究センター(UTCMES)では、日・オマーン外交関係樹立50周年事業として公開シンポジウム「深掘り! オマーン・スルタン国」を対面・オンライン併用で開催します。
このシンポジウムには、どなたでも無料でご参加頂くことができます。
皆さまぜひご参加ください。
UTCMES公開シンポジウム「深掘り! オマーン・スルタン国」
日時:2022年11月13日(日曜日)14時~17 時
場所:東京大学駒場キャンパス21KOMCEE West 地下1階レクチャーホール(オンライン配信あり)
◎プログラム
開会挨拶 モハメッド・アルブサイディ(駐日オマーン・スルタン国特命全権大使)
講演
・宮下純夫(新潟大学・名誉教授/NPO法人 北海道総合地質学研究センター・理事長)
「アラビア半島オマーンの自然と地質そして人々」
・近藤康久(総合地球環境学研究所・准教授)
「オマーンの考古遺産:文化の長期持続性と変容」
使用言語:日本語
参加無料・ 要事前申込 → https://park.itc.u-tokyo.ac.jp/UTCMES/2022/09/22/public_symposia/?fbclid=IwAR3OwlcHJcrEoOWYLINvingoNEcAyz6rjxm3K6P-iYVHCKsk7MfgckV_uB0
主催:東京大学中東地域研究センター(UTCMES)
共催:駐日オマーン・スルタン国大使館
後援:日本オマーン協会、広島オマーン友好協会、奈良オマーン友好協会、日本オマーンクラブ
問い合わせ:東京大学中東地域研究センター(UTCMES)
03-5465-7724 / info@utcmes.c.u-tokyo.ac.jp
2022年11月5日開催ギャラリートーク:オマーンの青銅器時代:文化と社会の変容
イベントの案内をいただきましたので、お知らせします。
***********************************
UTCMES・駒場博物館ギャラリートーク(第2回)オマーンの青銅器時代:文化と社会の変容
東京大学中東地域研究センター(UTCMES)では、日・オマーン外交関係樹立50周年事業として駒場博物館「オマーン展」を開催しています。
展示に関わるギャラリートークの第2回目では、講師に総合地球環境学研究所の黒沼太一先生をお迎えし、「オマーンの青銅器時代:文化と社会の変容」とのタイトルでお話を頂きます。
皆さまぜひご参加ください。
日時:2022年11月5日(土)15時~16時30分
場所:東京大学駒場キャンパス18号館 4階コラボレーションルーム3
※ ZOOMによるオンライン参加も可能です。
講演者:黒沼太一(総合地球環境学研究所・外来研究員/日本学術振興会・特別研究員PD)
言語:日本語
参加無料・要申込→ https://park.itc.u-tokyo.ac.jp/UTCMES/2022/10/01/gallery_talk_221020/?fbclid=IwAR333cHBIf7LftlhBBdzEnS7sv8H3w5QqgsjRxKKjNdF2dvZVZEIqWSquOg
主催・問い合わせ先:東京大学中東地域研究センター(UTCMES)
03-5465-7724 / info@utcmes.c.u-tokyo.ac.jp
2022年10月28日開催オンライン研究会「イラク・クルディスタンで新アッシリア帝国時代の拠点都市を掘る:ヤシン・テペ遺跡の最新成果から見る都市構造」
オンライン研究会の案内をいただきましたので、お知らせします。
***********************************
新学術領域研究「都市文明の本質」におきまして、オンライン研究会が行われますので、お知らせいたします。
————————————————————————–
A02-計画研究02第22回研究会
計画研究02「古代西アジアにおける都市の景観と機能」による第22回研究会を開催します。
日時:2022年10月28日(金)18:00-19:30
会場:Zoomを用いたオンライン開催
発表者:西山 伸一 (中部大学人文学部)
「イラク・クルディスタンで新アッシリア帝国時代の拠点都市を掘る:ヤシン・テペ遺跡の最新成果から見る都市構造」
※ オンライン参加をご希望の方は、10月27日(木)までにrcwasia[@]hass.tsukuba.ac.jp (「西アジア都市」事務局:土日は非対応)宛てのメールでご連絡ください。
新学術ホームページ
日本語 https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city/seminar/index.html?fbclid=IwAR1nHJG_xzCzTzxg0AY1nrd2XnXqOMHdi99VHtho_A382XuumhWgb9rcxK8#A02-02_22
English https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city_EN/seminar_EN/index_EN.html?fbclid=IwAR0H0k7Ie3cBnJ08vgM68fQMx25mAtOOUnwI4m-296nMDKs-FpGvlsv8V5k#A02-02_22
————————————————————————–
皆様のご参加をお待ちしております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
西アジア文明研究センター事務室
***********************************************************************
科学研究費補助金 新学術領域研究(研究領域提案型)
「西アジア都市」事務室
〒305-8571 茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学西アジア文明研究センター
029 853 5441
rcwasia@hass.tsukuba.ac.jp
2022年10月17日開催講演会:Detecting regionalism in Graeco-Roman cartonnage from the Western Egyptian Desert via multi-disciplinary investigation
講演会の案内をいただきましたので、お知らせします。
対面での開催となっており、3Dモデルを駆使した考古学研究の例として興味深い内容とのことです。
***********************************
金沢大学エジプト学特別講演会 2022-2
金沢大学古代文明・文化資源学研究所 / 新学術創成研究機構 共催
金沢大学国際共同研究スプラウティング支援
日時:2022年10月17日(月)16:30~18:00
場所:人間社会第2講義棟 402教室
題目:Detecting regionalism in Graeco-Roman cartonnage from the Western Egyptian Desert via multi-disciplinary investigation
講演者:Dr. Carlo Rindi Nuzzolo (Centre for Ancient Cultures, Monash University, Melbourne)
Abstract:
Excavation by The Dakhleh Oasis Project at the village of ancient Kellis (modern Ismant al-Kharab, Dakhleh Oasis) discovered an extensive cemetery with hundreds of rock-cut tombs with multiple interments. The primary feature of the area, known as Kellis 1 cemetery , is the presence of richly-decorated cartonnage (mummy masks, foot-cases, full body covers) with which the bodies were equipped. Although many intact pieces were discovered at the site, a considerable quantity of artefacts was found shattered due to tomb reuse and robbery, whether in ancient or modern times. The present talk will focus on the multi-disciplinary investigation carried out so far to overcome this and other obstacles to the scientific research, to clarify their stylistic and craftsmanship features, and to identify lost pieces originating from this archaeological area.
連絡先:河合 望 (nozomu.kawai@staff.kanazawa-u.ac.jp)