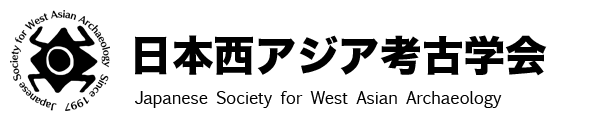2023年3月5日開催:フェニキア・カルタゴ研究会第8回公開報告会
研究会の案内をいただきましたので、お知らせします。
***********************************
フェニキア・カルタゴ研究会第8回公開報告会
お蔭様で公開報告会も今年で8回目を迎えることになりました。前半では、昨年10月にイビサ島で開催された第10回フェニキア・カルタゴ国際学会の報告に次いで、フェニキア人の本拠地、レバノンの発掘で出土した呪詛板についての研究報告をお話しいただきます。さらに高校の現場から、フェニキア・カルタゴ史についての実践報告を、現職の教員・高校生も参加して小シンポジウムという形で行います。後半では、今年度チュニジアで行われた現地調査の成果を、科研のテーマをもとにご発表いただきます。今回もさまざまな方向性からフェニキア・カルタゴ研究の「今」に迫りたいと思います。 是非、多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。
日時:2023年3月5日(日)13:30-16:00
プログラム
13:15 入室開始
13:30 開会の辞・趣旨説明 佐藤育子
13:35-13:50 第1報告 佐藤育子(日本女子大学)
「第10回フェニキア・カルタゴ国際学会に参加して」
13:50-14:25 第2報告 前野弘志(広島大学)
「2010年レバノン南部の都市ティール郊外地下墓TJ.10出土呪詛板の研究」
14:25-15:00 第3報告 丸小野壮太(常磐大学高等学校) 岩田和樹・薗部悠真・小宅進実 (常磐大学高等学校)
「小シンポジウム 高校におけるフェニキア・カルタゴ史研究」
15:00-15:00 休憩
15:10-15:45 第4報告 大清水裕(滋賀大学)
「ドゥッガとウキ・マイウスに見るローマ市民入植の諸相:2022年度チュニジア現地調査から」
15:45-16:00 質疑応答 司会 青木真兵
16:00 閉会
主催 フェニキア・カルタゴ研究会
共催 古代ローマ期北アフリカの農業に関する学際的研究
JSPS 科研費 21H00584 (研究代表者 大清水 裕)
参加をご希望の方は、3月3(金)までに下記の フォームからお申込み下さい。
3月4日(土)までに 当日のリンク先など参加方法をお知らせします
https://forms.gle/zAw9yKVixTJEa1889
ご不明な点などございましたら、下記までお問合せください。
佐藤育子
isatou@fc.jwu.ac.jp
2023年3月30日開催:Tlos遺跡ワークショップ ※中止となりました
1月24日付で、ワークショップのお知らせとして配信しました下記の催しについて、中止の連絡がありましたのでお知らせします。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
日本西アジア考古学会メーリングリストに登録されていらっしゃる皆様におかれましては、ご健勝のこととお喜び申しあげます。
かねて、ご案内を差し上げておりましたシンポジウムUrbanism and Ruralism in Tlos ですが、本日、登壇予定であったタネル・コルク—ト教授以下3名の先生から、来月下旬の訪日予定をキャンセルしたいとのご連絡をいただきました。
昨日も余震が相次ぎ、トルコ国内では、人々の精神的なショックは大きくなるばかり。今、この時期は、とても国外に出かけられるような状況にはなく、ご親族、智人、同胞の死や苦境とともにありたいとご希望です。
私共といたしましても、誠に残念ではありますが、2011年の際のことを思い出すにつけ、トルコの被災地の状況には心が痛むばかりです。皆様におかれましても、どうか上記事情をご賢察いただけますと幸いです。また、私が申し上げるべきことかどうか悩みますが、長らくトルコの方々と親交を結んでまいりましたひとりとして、様々なルートで現地の方々への援助が提供されておりますこと、末筆ながらご案内させていただきます。
浦野聡
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ワークショップの案内をいただきましたので、お知らせいたします。
3月30日、トルコの古代遺跡トロスの発掘調査隊を招いて、15年間の発掘成果のご紹介をいただくことになりました。
トロスは、ヘレニズム期以降に都市的な景観を示し始め、ビザンツ時代中期まで、連綿として都市的な営みを続けましたが、町の中心部を占めるスタディオンからは、ヒッタイト期に遡る遺構・遺物も発見されています。また、トロス遺跡は、都市の農村領域内に、10000BPの新石器遺跡(Gilmeler)も抱えており、これは、アナトリアの地中海岸を通じてレヴァントからヨーロッパへ現生人類が移動したことを示す初めての証拠として世界的にも注目されました。
古典考古学者は、どうしても、観光資源になりうる都市遺構の発掘を優先するように政府から求められがちなのですが、近年の、ベルギー隊のサガラッソス発掘等に刺激を受ける形で、トルコ国内でも、数十キロ圏内の古代都市領域を含めた調査も現れ始めています。トロス発掘調査隊は、そうした調査に早くから取り組んできており、時代的のみならず、地理的なスコープの広さの点でも、トルコ国内の考古学発掘隊の中でもユニークな地位を占めるチームです。当日、その成果の一端を示していただくとともに、様々な知見を交換することができれば幸いです。
プログラム
発表① 14:00-15:00
TANER KORKUT (AKDENIZ UNIVERSITY)
Title: URBANISM OF TLOS. HISTORY OF A LYCIAN CITY FROM PREHISTORIC TO MODERN TIMES.
発表② 15:00-15:30
ÇILEM UYGUN (HATAY MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY)
Title: THE NECROPOLEIS AND ITS ARCHITECTURE AT TLOS IN WESTERN LYCIA.
発表③ 15:30-16:00
BILSEN ÖZDEMİR (HACI BEKTAŞ VELI UNIVERSITY)
Title: WINE AND OLIVE OIL PRODUCTION AND TRADE IN TLOS.
16:00-17:00 Discussion (Chair: Akiko Moroo)
英語でお話しいただくことをお願いしていますが、英語でのコミュニケーションに不慣れでいらっしゃいます。
できるだけ緊張のないざっくばらんな形でのコミュニケーションを心がけますので、ご参加をお待ちしております。
なお、簡単な報告要旨を用意しております。会場準備の都合もあり、ご出席のメールを下記アドレス宛てにいただいた方に、ご出欠確認も兼ねて配布することとさせていただきたく存じます。もちろん、出席はできないけれど、要旨のみご所望という場合にも対応をいたしますので、ご遠慮なくお申し越しいただければ幸いです。
参加申し込み先 浦野聡 uran@rikkyo.ac.jp
また、以下は、同発掘隊の出版一覧です。
Publications | Tlos Antik Kenti Kazıları (akdeniz.edu.tr)
2023年2月14日開催国際ワークショップ:「中央アジア東部地域での定住集落の出現」
国際ワークショップの案内をいただきましたので、お知らせします。
***********************************
国際ワークショップ 中央アジア東部地域での定住集落の出現
開催趣旨:
近年の考古学調査の進展により、西アジアから中央アジアへの農耕牧畜文化の波及にかんする考古学的証拠は格段に増加した。特に、これまで資料が手薄であった中央アジア東部地域での最古の家畜の年代が紀元前6000年頃に遡る新発見は記憶に新しい。
一方、地域によっては周辺と比べて農耕牧畜の導入が著しく遅れる地域も存在する。砂漠、山地、ステップなどがモザイク状に入り組む独特の自然環境のほか、食料生産経済が最も早く進行したもう一つの核地帯である中国と接するその地理的位置が、中央アジア東部地域での農耕牧畜の受容や生業のあり方に多様性をもたらしているとも考えられる。
本ワークショップでは、中央アジア東部の新石器化に関する最新の研究動向を踏まえつつ、農耕牧畜とならぶ新石器化の指標である定住について着目する。中央アジア東部最古の農村の一つであるウズベキスタン、フェルガナ盆地のダルヴェルジン遺跡の生業に関する最新の研究成果から、この地域で定住村落が出現した背景について考える機会としたい。
日時:2023年2月14日(火) 13:00-16:30
開催方式:対面(金沢大学)・オンライン(Zoom)
参加方法:要事前登録。下記の問い合わせ先までメールにてお申込ください(2/13締切)
言語:日本語・英語(通訳なし)
主催:科研費基盤研究A「原シルクロードの形成」研究グループ
共催:金沢大学古代文明・文化資源学研究所、科研費学術変革領域研究A「中国文明起源」(代表:中村慎一)
プログラム
13:00-13:10 開会挨拶・趣旨説明
久米正吾(金沢大学)
13:10-13:40 キジルクム砂漠とその周辺の「新石器化」:ウズベキスタンのアヤカギトゥマ遺跡(ケルテミナル文化)
ヒクマトゥッラー ホシモフ(サマルカンド考古学研究所)
13:40-14:10 ダルヴェルジン遺跡:フェルガナ盆地の「新石器化」と青銅器時代における定住のはじまり
久米正吾(金沢大学)
14:10-14:40 中央アジア東部での初期の雑穀利用と乳利用:ダルヴェルジン遺跡出土土器脂質分析
宮田佳樹(東京大学)
14:40-15:00 休憩
15:00-15:30 中央アジア東部への家畜の波及とダルヴェルジン遺跡での家畜飼育
新井才二(東京大学)
15:30-16:00 安定同位体分析によるダルヴェルジン遺跡出土家畜の食性評価
覚張隆史(金沢大学)
16:00-16:30 自由討論
お問い合わせ・事前登録
金沢大学古代文明・文化資源学研究所
久米正吾(shogo_kume@staff.kanazawa-u.ac.jp)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
International workshop
Considering the emergence of village life in eastern Central Asia
Date: February 14, 2023 (Tue.) 13:00-16:30
Venue: Kanazawa University and online (Zoom)
Program
13:00-13:10 Opening remarks Shogo Kume (Kanazawa University)
13:10-13:40 “Neolithization” in the Kyzylkum Desert and beyond: A Kelteminar site of Ayakagytma in Uzbekistan
Hikmatullar Hoshimov (Samarkand Institute of Archaeology)
13:40-14:10 Dalverzin: “Neolithization” and early sedentarization in the Fergana Valley in the Bronze Age
Shogo Kume (Kanazawa University)
14:10-14:40 Early millet and milk utilization in Eastern Central Asia: Lipid analysis in pottery from the Dalverzin Site
Yoshiki Miyata (The University of Tokyo)
14:40-15:00 Coffee break
15:00-15:30 Dispersal of domestic ungulates into the Eastern Central Asia and livestock economy at Dalverzin
Saiji Arai (The University of Tokyo)
15:30-16:00 Reconstruction of diet signature in Dalverzin site using stable isotope analysis
Takashi Gakuhari (Kanazawa University)
16:00-16:30 Discussion
Contact:
Shogo Kume (shogo_kume@staff.kanazawa-u.ac.jp)
Institute for the Study of Ancient Civilizations and Cultural Resources, Kanazawa University
2023年2月21日・22日開催:パレスチナ観光プロモーションイベント
パレスチナ関連のイベントの案内をいただきましたので、お知らせします。
***********************************
—中東最大のモザイクが1300年の時を経て目を覚ますー
知られざる魅力に迫る「パレスチナ観光プロモーションイベント」のご案内
<名古屋・大阪で開催!>
パレスチナは、文化遺跡や豊かな自然、美食、アートなどの魅力的な観光資源を豊富に有しています。
その魅力について日本ではまだあまり知られておらず、日本の皆さまにご紹介させていただきたいと思います!
▼パレスチナの魅力とは—————————————————
・3つの世界遺産
・イスラム教・キリスト教・ユダヤ教の聖地であるエルサレム
・中東一の規模を誇る約900㎡のモザイク床を鑑賞できるヒシャム宮殿
・死海などの豊かな自然
・バンクシーが手掛けた「世界一眺めの悪いホテル」や壁画
・ヨルダンとイスラエルといった周辺国と合わせて訪れることもできます!
——————————————————————————
パレスチナの知られざる魅力を見て・触れて・体験できる「パレスチナ観光プロモーションイベント」を開催します!ポテンシャル溢れるパレスチナに触れることができるこの機会に、奮ってご参加ください!
▼本イベントの見どころ————————————————————————————
★パレスチナから観光遺跡庁大臣をはじめ、観光業関係者が来日し、パレスチナ観光の魅力と現地の最新状況をご紹介します!
★パレスチナの食や工芸、伝統衣装に触れてみませんか?
★中東一の規模を誇るヒシャム宮殿遺跡のモザイクを、日本にいながら体感できるVR(仮想現実)を体験できます!
★ご来場者いただき、アンケートにお答えいただいた方にお土産をプレゼント!
—————————————————————————————
◆◆◆
※名古屋※
【開催日時】 2023年2月21日(火)17:30〜19:30(受付開始:16:30〜)
【会場】 国際協力機構(JICA)名古屋地球ひろば セミナールームA
愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-7⇒リンク
※大阪※
【開催日時】 2023年2月22日(水)17:30〜19:30(受付開始:16:30〜)
【会場】オービックホール御堂筋ビル2F ホールC(予定)
大阪府大阪市中央区平野町4丁目2-3⇒リンク
【対象】※参加費無料
・中東地域、パレスチナ、イスラム文化に関心がある方
・いつか、中東地域、パレスチナに行ってみたいけれども、どうすればいいか分からない!という方
【プログラム】
「観光プロモーショ ンセッション」(17:00〜18:30)
★開会挨拶(JICA事務局)
★パレスチナ観光遺跡庁大臣ご挨拶
★パレスチナ、ヨルダンより来日した観光団体、JICA観光専門家がパレスチナ観光の魅力や最新情報をご紹介します。
「パレスチナ体験」コーナー(18:30〜19:30)
・ワインやおつまみといった、パレスチナ産品をご賞味いただけます。
・2021年8月から新規公開された、中東一の約900㎡の規模を誇るヒシャム宮殿のモザイク床をVR(仮想現実)で至近距離から体験できます!!
※内容は予告なく変更される場合があります。※オンライン同時配信は予定しておりません。
【お申込】 2023年2月15日(水)17時までに、こちらのフォームまでお申し込みください。
<お申込みに関するお問合せ先>
JICA 課題部支援ユニット(Email:Kadaishien_chosei@jica.go.jp)
2023年2月23日開催:シンポジウム「前田耕作先生の業績を語る会」
文化遺産国際協力コンソーシアムのメールニュース掲載された、故前田耕作先生に関するシンポジウムです。
主催者側に問い合わせたところ、コンソーシアムの会員以外も参加できる公開シンポジウムとのことですので、お知らせします。
***********************************
シンポジウム「前田耕作先生の業績を語る会」開催のお知らせ【開催:2023年2月23日(木)】
●趣旨:
「私は書物の頁をふせる。バーミヤンを去るときがきたのだ。」『巨像の風景』末尾より
先生が、1964年に、仏縁とも思われる機会でアフガニスタンの調査に参加することになり、以来、バーミヤン、アレクサンドロス、ギリシア、ローマ、玄奘、仏教・・・など、東西南北のシルクロードについて、私たちにその考究を語っていただきました。その思いは予定された講演時間に収まることはありませんでした。
文章では、ギリシア語、フランス語、現地語などを踏まえ、詩的で、あるものは一編の小説を思わせるものがありました。先生の膨大な知識に触れることができなくなりました。
ご遺族の方にお願いして、先生を慕う人たちとともに業績を語る会を、下記のとおり開催する運びとなり、ここにご案内申し上げます。
●日時:2023年2月23日(木)13:00〜16:30 *受付12:00より
●会場:東京国立博物館平成館大講堂 *大講堂へは西門よりお入りください。
●参加費:2000円 *当日、会場受付にてお支払いください。
●申込方法(事前申込制):氏名・連絡先メールアドレスおよび電話番号を明記し、下記のメールアドレス宛にお申込みください。
申し込み先:aokisigeo@nifty.com
●申込締切:2023年2月4日(土)
●詳細内容は下記のURLをご覧ください。
https://www.jcic-heritage.jp/20221223news/
2023年2月11日開催:古代メソポタミア講演会
講演会の案内をいただきましたので、お知らせいたします。
***********************************
2月11日(土)に、イギリス、マンチェスター大学の2名の研究者による古代メソポタミア講演会を開催します。
考古学者のスチュアート・キャンベル氏は、南メソポタミア前2千年期におけるSealand Dynastyの都市であるTell Khaiber遺跡の最新の発掘成果について講演されます。
アラム語(シリア文字、ナバテア文字)を専門とし、大英博物館双書『初期アルファベット( 失われた文字を読む)』の著者でもあるジョン・ヒーリー氏は、ローマ時代のアラム語碑文に見られる古代メソポタミア世界について講演されます。
参加無料、事前登録不要です。皆様のご参加をお待ちしております。
(講演は英語でおこなわれます。通訳はありません)
日時:2023年2月11日(土)16:00~18:00
場所:筑波大学東京キャンパス(茗荷谷)121講義室
アクセス:https://www.tsukuba.ac.jp/access/tokyo-access/index.html
地下鉄丸ノ内線 茗荷谷駅から徒歩3分(東京都文京区大塚3-29-1)
プログラム
Opening remarks:Osamu Maeda (University of Tsukuba)
Stuart Campbell (Prof. University of Manchester)
”Tell Khaiber; Intersecting Communities in the Sealands of Southern Mesopotamia”
John Healey (Emeritus Prof. University of Manchester)
”The Ancient Mesopotamian Heritage in Roman-era Aramaic Epigraphy”
*プログラム、フライヤーPDFは、筑波大学西アジア文明研究センターのホームページからもご覧いただけます。
https://rcwac.histanth.tsukuba.ac.jp/events/event/20230211
お問い合わせは、筑波大学 前田修(maeda.osamu.gm@u.tsukuba.ac.jp)までお願いします。
2023年1月26日開催オンライン講演会”Urbanism in a changing Egyptian Landscape”
オンライン研究会の案内をいただきましたのでお知らせします。
***********************************
科研費新学術領域研究「都市文明の本質」におきまして、下記の研究会が行われますので、お知らせいたします。
計画研究03「古代エジプトにおける都市の景観と構造」による第11回研究会
日時:2023年1月26日(木)19:00-20:30
会場:Zoomを用いたオンライン開催
発表者:Dr. Judith Bunbury (University of Cambridge)
発表題目:“Urbanism in a changing Egyptian Landscape”
※ オンライン参加をご希望の方は、1月25日(水)までにrcwasia@hass.tsukuba.ac.jp (「西アジア都市」事務局:土日は非対応)宛てのメールでご連絡ください。
新学術ホームページ
日本語 https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city/seminar/index.html#A02-03_11
English https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city_EN/seminar_EN/index_EN.html#A02-03_11https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city/
https://rcwac.histanth.tsukuba.ac.jp/
2023年1月20日開催オンライン懇話会「真珠から見た大航海時代——海の宝石のグローバルヒストリー」
オンライン懇話会の案内をいただきましたのでお知らせします。
***********************************
*日本学術振興会カイロ研究連絡センター定例懇話会**(Online)*
*(**2022**年度第**9**回のお知らせ)*
前略、年の瀬も押し詰まり、お忙しい日々をお過ごしのことと存じます。この度は、2021年に真珠史研究により大阪大学で博士号を取得され、去る11月に博士論文に基づく『真珠と大航海時代』を出版された山田篤美氏に、真珠の歴史についてお話をいただけることになりました。山田氏は京都大学をご卒業後、オハイオ州立大学大学院にてイスラーム美術史などを専攻され『ムガル美術の旅』(1997年)を上梓。その後研究分野を広げられ、南米への欧州進出の近世史『黄金郷伝説』(2008年)を刊行、さらにグローバルな視点から真珠に着目して『真珠の世界史』(2013年)をまとめられ、精力的に研究を続けられました。ぜひ多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
草々
◆ 日時:2023年1月20日(金)開始時間:カイロ13時から(日本時間20時から)
講演:60分 質疑応答:30分
◆ 配信方法:zoom
◆ 講演:「真珠から見た大航海時代——海の宝石のグローバルヒストリー」
◆ 講師:山田 篤美(やまだ あつみ)文学博士(大阪大学)、歴史研究者
◆ 要旨(講師記)
大航海時代にはスパイスと黄金が求められたと説明されますが、当時の法令や公文書を分析し、真珠の観点から大航海時代を見ると、従来の解釈とは異なる事象が明らかになります。ポルトガル領インドでは、イエズス会やポルトガル海軍が関与する真珠採取業という水産業が実施され、ゴアは新世界の真珠までも集めるグローバル市場になりました。その新世界ではスペイン人による奴隷制真珠採取業が興り、真珠による大西洋奴隷貿易が
16世紀前半に形成されていたのです。今回の発表は、『真珠と大航海時代』(山川出版社)をベースにあまり知られていない真珠の歴史を語ります。
なぜ真珠が歴史学で看過されたかについては、世界史研究所の「世界史の眼」ウェブサイトをご覧ください。
https://riwh.jp/category/eye/
本の表紙には、西洋の女神に真珠が献上されているイギリス東インド会社の天井画を使っていますので、こちらもご覧ください。
●参加方法:講演は無料となっております。
参加希望者は、氏名(フルネーム)と所属、*第**9**回*を明記の上、メール*jspslecmet@gmail.com
*宛に前日までに必ずお申込みください。ZoomのURL、ID、パスワードをこちらより後日連絡いたします。
※今回の講演は*金曜、カイロ時間**13**時(日本時間**20**時)*に*オンラインのみ*で開催いたしますので、曜日・時間帯・参加方法をお間違えのないようにご注意ください
2023年1月17日開催オンライン講演会「東アジア都城の系譜—『周礼』考工記から藤原・平城京まで」
オンライン研究会の案内をいただきましたのでお知らせします。
***********************************
科研費新学術領域研究「都市文明の本質」におきまして、下記の研究会が行われますので、お知らせいたします。
C01-計画研究05 第32回研究会
計画研究05「中世から近代の西アジア・イスラーム都市の構造に関する歴史学的研究」による第32回研究会を開催します。
「都市とは何か」を検討するにあたり、さまざまな地域や時代の歴史をご専門とされる先生方をお招きして、オンライン(Zoom)による連続講演会「都市の世界史」を開催しております。第9回は下記の要領で行います。
日時:2023年1月17日(火)19:30〜21:00
講師:佐川 英治 先生(東京大学大学院人文社会系研究科)
テーマ:「東アジア都城の系譜—『周礼』考工記から藤原・平城京まで」
【講師紹介】
東京大学大学院人文社会系研究科教授。専門は中国古代史。著書に『中国古代都城の設計と思想』(勉誠出版、2016年)、『中国と東部ユーラシアの歴史』(共著、放送大学教育振興会、2020年)、『ビジュアル大図鑑 中国の歴史』(監修、東京書籍、2022年)などがある。
*今回は、7世紀末に造られた日本初の中国式都城である藤原京と平城京の都城制を中国の歴史にさかのぼり、その変化を広く東アジアの都城の系譜のなかに位置づけてお話しいただきます。
申込先:https://forms.gle/oX9skGPqnk3xaejD7
*Googleフォームでの申し込みとなります。前日の1月16日正午までに、上記のURLからお申し込みください。
*お申し込みいただいた方へ、前日中に、当日のURL(Zoom)をお送りいたします。
本連続講演会は、新学術領域研究「都市文明の本質:古代西アジアにおける都市の発生と変容の学際研究」計画研究「中世から近代の西アジア・イスラーム都市の構造に関する歴史学的研究」(代表:守川知子)にて行ってきた「西アジア都市研究」を発展させたものです。ご講演は45〜50分、質疑応答は35〜40分と、ディスカッションを重視した時間配分となっております。奮ってご参加くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
【これまでの講演会】
第1回・4月22日(金) 深見奈緒子先生(日本学術振興会カイロ研究連絡センター)「都市の歴史:生態圏と形態・人口」
第2回・5月24日(火) 森本公誠先生(東大寺)「アラブの軍営都市(ミスル)」
第3回・6月21日(火) 菅谷成子先生(愛媛大学)「スペイン植民地都市マニラ」
第4回・7月15日(金) 森安孝夫先生(大阪大学)「中央ユーラシアのオアシス都市と草原都市」
第5回・9月27日(水) 稲葉穣先生(京都大学)「都市と山岳フロンティア」
第6回・10月21日(金) 深沢克己先生(東京大学・日本学士院)「地中海都市の歴史像——マルセイユの事例から」
第7回・11月25日(金) 松井洋子先生「近世日本の貿易都市長崎」
第8回・12月13日(火) 常木晃先生(筑波大学)「西アジアにおける都市の始まりと物資管理システム」
【今後の予定】
第10回・3月3日 南川高志先生(佛教大学)
皆様のご参加をお待ちしております。
守川知子 tomomo[@]l.u-tokyo.ac.jp
日本語 https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city/seminar/index.html#C01-05_32
English https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city_EN/seminar_EN/index_EN.html#C01-05_32
新学術「西アジア都市」総括班事務局
小松崎礼子
**************************************************************************
科学研究費補助金 新学術領域研究(研究領域提案型)
「西アジア都市」事務室
〒305-8571 茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学西アジア文明研究センター
029 853 5441
rcwasia@hass.tsukuba.ac.jp
https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city/
https://rcwac.histanth.tsukuba.ac.jp/
2022年12月26日開催オンライン研究会「第3中間期の都市・アコリスにおける交易活動ータカラガイを中心にー」
オンライン研究会の案内をいただきましたのでお知らせします。
***********************************
科研費新学術領域研究「都市文明の本質」におきまして、下記の研究会が行われますので、お知らせいたします。
計画研究03「古代エジプトにおける都市の景観と構造」による第10回研究会(講演会)
日時:2022年12月26日(月)19:00~20:30
会場:Zoomを用いたオンライン開催
発表者:辻村 純代(公財)古代学協会
題目:「第3中間期の都市・アコリスにおける交易活動ータカラガイを中心にー」
※ 参加をご希望の方は、12月23日(金)までにrcwasia@hass.tsukuba.ac.jp
(「西アジア都市」事務局:土日は非対応)宛てのメールでご連絡ください。
皆様のご参加をお待ちしております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
「西アジア都市」ホームページ
日本語 https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city/seminar/index.html#A02-03_10
English
https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city_EN/seminar_EN/index_EN.html#A02-03_10
******************************************************
科学研究費補助金 新学術領域研究(研究領域提案型)
「西アジア都市」事務室
〒305-8571 茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学西アジア文明研究センター
029 853 5441
rcwasia@hass.tsukuba.ac.jp
https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city/
https://rcwac.histanth.tsukuba.ac.jp/
2023年1月20日開催オンライン研究会「初期王朝時代ラガシュの王妃の家 The House of the Queen in Presargonic Lagash」
オンライン研究会の案内をいただきましたのでお知らせします。
***********************************
新学術領域研究「都市文明の本質」におきまして、オンライン研究会が行われますので、お知らせいたします。
———————————————————————————————————————
A02-計画研究02第25回研究会
計画研究02「古代西アジアにおける都市の景観と機能」による第25回研究会を開催します。
日時:2023年1月20日(金)18:00-19:30(JST)/11:00-12:30(EET)
会場:Zoomを用いたオンライン開催
発表者:唐橋 文 (中央大学)
「初期王朝時代ラガシュの王妃の家 The House of the Queen in Presargonic Lagash」
※ オンライン参加をご希望の方は、2023年1月18日(水)までにrcwasia[@]hass.tsukuba.ac.jp (「西アジア都市」事務局:土日は非対応)宛てのメールでお申し込みください。
新学術ホームページ
日本語 https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city/seminar/index.html#A02-02_25
English https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city_EN/seminar_EN/index_EN.html#A02-02_25
——————————————————————————————————————–
皆様のご参加をお待ちしております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
西アジア文明研究センター事務室
**************************************************************************
科学研究費補助金 新学術領域研究(研究領域提案型)
「西アジア都市」事務室
〒305-8571 茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学西アジア文明研究センター
029 853 5441
rcwasia@hass.tsukuba.ac.jp
2023年1月21日・22日開催:シルクロード学研究会 2023冬
研究会の案内をいただきましたのでお知らせします。
***********************************
シルクロード学研究会 2023冬
日時:2023年1月21日(土)・22日(日)
主催:帝京大学文化財研究所/キルギス共和国国立科学アカデミー
会場:帝京大学文化財研究所大ホール/Zoomウェビナー(ハイブリッド)
申し込み締切:(現地参加)2023年1月8日(日)/(オンライン)2023年1月18日(水)
*感染状況に応じてオンラインのみの開催になる可能性があります
参加フォーム: https://forms.gle/Sn7y4fRHoiUBG3CG7
問い合わせ先:teikyo.silkroad@gmail.com
〒406-0032 山梨県笛吹市石和町四日市場1566-2 電話055-261-0015
※研究所へはJR 石和温泉駅から徒歩で約25 分、タクシーで約8 分、駐車場あり
※本研究会はJSPS 科研費21H04984(基盤研究(S))の助成を受けています
テーマ:遊牧民と定住民の接点を探る
日程:
1日目(13:00~17:30)
13:00~13:10 開会挨拶
13:10~13:50 山内 和也(帝京大学)
スイヤブをめぐる遊牧民と定住民
13:50~14:30 吉田 豊(帝京大学)
ソグド人と遊牧民の関係を示すソグド語資料について
14:30~15:10 齊藤 茂雄(帝京大学)
モンゴル高原~北中国におけるトルコ系遊牧民と定住民
15:10~15:20 休憩
15:20~16:00 古松 崇志(京都大学)
契丹(遼)における都市と定住民
16:00~16:40 森部 豊(関西大学)
唐の「羈縻」支配と契丹
16:40~17:30 総合討論(司会:山内 和也・吉田 豊)
2日目(9:00~12:00)
9:00~9:40 山藤 正敏(奈良文化財研究所)
南レヴァントにおける都市の興亡と遊牧民:前4~3千年紀の異生業間ダイナミズム
9:40~10:20 大谷 育恵(京都大学)
遊牧国家・匈奴と秦漢帝国のあいだ:近年の匈奴考古学の成果を中心に
10:20~11:00 白石 典之(新潟大学)
カラコルム都市圏における遊牧と定住
11:00~11:10 休憩
11:10~11:50 総合討論(司会:山内 和也・吉田 豊)
11:50~12:00 閉会挨拶