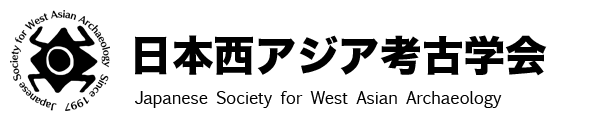2019年6月24日(月)開催:国士舘大学「ハイダル博士里帰り報告会」
バビロン大学教授のハイダル氏、クーファ大学教授のナシャット氏をお招きして研究会を開催いたします。
是非ご参加頂ければと思います。会場の都合もございますので、下記連絡先に参加の御連絡を頂ければと思います。
※英語での報告となりますので、ご了承ください。
ハイダル博士里帰り報告会
日時:2019年6月24日(月)16時15分〜18時
場所:国士舘大学町田キャンパス図書館4階、ラーニングコモンズ
申込先・連絡先:kuiraq@kokushikan.ac.jp
<報告会次第>
•報告者:
ハイダル・アルマモリ博士(イラク、バビロン大学教授)
ナシャット・アルハファジ博士(イラク、クーファ大学教授)
•時程:
16:15 イラク研所長挨拶と報告者紹介
16:30 ハイダル博士報告
17:15 ナシャット博士報告
17:45 質疑と閉会
2019年6月23日(日)開催:オリ博講演会「危機にあるシリア文化遺産の記録」
【オリ博講演会】「危機にあるシリア文化遺産の記録」
シリアにおける内戦は8年以上が経過し、シリア各地の文化遺産は、戦災や盗掘、略奪、あるいは石取りなど様々な被害にあい、極めて深刻な状況に陥っています。内戦前までシリアの特にイドリブ県で長期にわたり考古学調査を継続してきた筑波大学の調査隊は、文化庁の支援を得て、危機にあるシリア文化遺産の保護に取り組んでいます。
今回はそのような活動の一つ、イドリブ県にある被災の激しい世界遺産(現在は世界危機遺産に指定)「北シリアの古代村落群」で行っている初期教会のデジタルデータによる記録などについて紹介します。重要な遺跡を最新の技術で正確に記録しておくことは、学術的な意味だけでなく、万が一それらが破壊された場合の復元にとっても、重大な意味を持っていると考えているからです。
日時 2019年 6月23日(日) 13:00-15:00
場所 池袋サンシャインシティ 文化会館7階 会議室710室
講師 常木 晃(筑波大学教授) 渡部展也(中部大学准教授)
参加費500円(古代オリエント博物館友の会会員は無料)
定 員:130名※正午より先着順。
※事前申込不要。直接会場へお越し下さい
講演会:http://aom-tokyo.com/event/190623.html
問合せ先:
古代オリエント博物館
Tel:03-3989-3491
Email:museumアットマークorientmuseum.com[@に直して送信下さい。]
なお、本講演は下記展示の関連講演です。
【クローズアップ展示】危機にあるシリア文化遺産の記録
8年以上続く内戦によって多くの文化遺産が破壊、盗掘、略奪などの被害にあったシリアにおいて、内戦前まで長期にわたって同地で考古学調査を継続してきた筑波大学が文化庁文化遺産保護国際貢献事業の委託を受けて実施したシリア文化遺産の記録事業や文化遺産の重要性に関する啓蒙活動について紹介し、その成果を広く公開します。
主に「北シリアの古代村落群」(世界危機遺産指定)でおこなっているデジタルデータ収集とそれに基づいた3Dイメージ制作について報告します。
併せて、アレッポ、パルミラ、イドリブ博物館などの被災映像や写真を通じて、シリア国内の被災状況や文化遺産の保護に懸命に取り組む人々の姿も紹介します。
会期 2019年6月8日(土)~2019年6月30日(日) ※休館日なし
開館時間
10:00~17:00(入館は16:30まで)
http://aom-tokyo.com/exhibition/190608_Syria.html
場所 古代オリエント博物館 (池袋サンシャインシティ 文化会館7階)
筑波大学・古代オリエント博物館共催、日本西アジア考古学会後援
2019年6月22日(土)開催:筑波大学科研費A02-計画研究02 第5回研究会「Recent Archaeological Research in Southern Iraq」
科研費新学術領域研究「都市文明の本質」におきまして、A02-計画研究02 第5回研究会が開催されますので、お知らせいたします。
なお、研究会の後には懇親会を予定しております。ご参加いただける方は下記までご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。
筑波大学 西アジア文明研究センター事務局
rcwasia@hass.tsukuba.ac.jp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A02-計画研究02 第5回研究会
「Recent Archaeological Research in Southern Iraq」
計画研究02「古代西アジアにおける都市の景観と機能」では、国士舘大学イラク古代文化研究所の後援を得て、イラク・バビロン大学のハイダル・アルマモリ先生とクーファ大学のネシャト・アルハファジ先生を招いたワークショップを開催します。
日時:2019年6月22日(土)13:00-17:00
会場:サンシャインシティ文化会館 709室(東京都豊島区東池袋3-1-4)
プログラム
13:00–14:00
Kazuya Maekawa (Kokushikan University, Kyoto University)
Gišša (alleged Umma) in Early Dynastic IIIb Sumer: A new perspective from new documents from the “Umma region”
14:30–15:30
Haider Almamori (University of Babylon)
Excavations at two Sumerian and Babylonian cities
16:00–17:00
Neshat Alkhafaji (Kufa University)
Three unpublished texts: Naram-Sin inscription, marriage contract and mathematical text
*申し込み不要、直接会場へお越しください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
下記ウェブサイトからもご覧いただけます。
なお、こちらからポスターをダウンロードできます。
日本語 http://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city/seminar/index.html#A02-02_05
英語 http://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city_EN/seminar_EN/index_EN.html#A02-02_05
皆様のご参加をお待ちしております。
西アジア文明研究センター事務局 上原・廣永
**************************************************************************
科学研究費補助金 新学術領域研究(研究領域提案型)
「西アジア都市」事務室
〒305-8571 茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学人文社会科学研究科歴史・人類学専攻事務室付
西アジア文明研究センター
029 853 5441
rcwasia@hass.tsukuba.ac.jp
2019年6月8日(土)~6月30日(日)開催:展示「危機にあるシリア文化遺産の記録」
古代オリエント博物館のクローズアップ展として、「危機にあるシリア文化遺産の記録」を開催することになりました。
【クローズアップ展示】危機にあるシリア文化遺産の記録
8年以上続く内戦によって多くの文化遺産が破壊、盗掘、略奪などの被害にあったシリアにおいて、内戦前まで長期にわたって同地で考古学調査を継続してきた筑波大学が文化庁文化遺産保護国際貢献事業の委託を受けて実施したシリア文化遺産の記録事業や文化遺産の重要性に関する啓蒙活動について紹介し、その成果を広く公開します。
主に「北シリアの古代村落群」(世界危機遺産指定)でおこなっているデジタルデータ収集とそれに基づいた3Dイメージ制作について報告します。
併せて、アレッポ、パルミラ、イドリブ博物館などの被災映像や写真を通じて、シリア国内の被災状況や文化遺産の保護に懸命に取り組む人々の姿も紹介します。
会期 2019年6月8日(土)~2019年6月30日(日) ※休館日なし
開館時間
10:00~17:00(入館は16:30まで)
http://aom-tokyo.com/exhibition/190608_Syria.html
場所 古代オリエント博物館 (池袋サンシャインシティ 文化会館7階)
筑波大学・古代オリエント博物館共催、日本西アジア考古学会後援
なお、このクローズアップ展に関連して、次のような講演会を行います。
【オリ博講演会】
「危機にあるシリア文化遺産の記録」
シリアにおける内戦は8年以上が経過し、シリア各地の文化遺産は、戦災や盗掘、略奪、あるいは石取りなど様々な被害にあい、極めて深刻な状況に陥っています。内戦前までシリアの特にイドリブ県で長期にわたり考古学調査を継続してきた筑波大学の調査隊は、文化庁の支援を得て、危機にあるシリア文化遺産の保護に取り組んでいます。
今回はそのような活動の一つ、イドリブ県にある被災の激しい世界遺産(現在は世界危機遺産に指定)「北シリアの古代村落群」で行っている初期教会のデジタルデータによる記録などについて紹介します。重要な遺跡を最新の技術で正確に記録しておくことは、学術的な意味だけでなく、万が一それらが破壊された場合の復元にとっても、重大な意味を持っていると考えているからです。
日時 2019年 6月23日(日) 13:00-15:00 ※事前申込不要。直接会場へお越し下さい
場所 池袋サンシャインシティ 文化会館7階 会議室710室
講師 常木 晃(筑波大学教授) 渡部展也(中部大学准教授)
参加費500円(古代オリエント博物館友の会会員は無料)
2019年3月25日(月)開催:アナトリア考古学研究所:2018年度トルコ調査報告会・第29回トルコ調査研究会
2018年度トルコ調査報告会・第29回トルコ調査研究会が開催されます
名 称:2018年度トルコ調査報告会・第29回トルコ調査研究会
趣 旨:
(公財)中近東文化センター附属アナトリア考古学研究所は、2018年5月〜1月初旬にかけて順次、第10次ビュクリュカレ発掘調査、第33次カマン・カレホユック発掘調査、第10次ヤッスホユック発掘調査を順次行いました。ビュクリュカレでは、ヒッタイトの都市の解明を、カマン・カレホユックでは「文化編年の構築」を目的とした発掘調査を継続し、ヤッスホユックでは、遺丘裾部の紀元前2千年紀の「下の町」の解明を意図した発掘調査を開始しました。
報告会では、2018年に行った3遺跡の発掘成果、研究会では発掘調査で出土した資料をもとに行われている研究についての発表を行います。
皆様には是非ご参加いただきたく、ご案内申し上げます。
日 時:2019年3月25日(月)13:00-16:30
2019年3月26日(火)10:30-16:15
場 所:学習院大学 目白キャンパス「創立百周年記念会館」講堂(3階)
(東京都豊島区目白1-5-1)
http://www.gakushuin.ac.jp/map.html
受 付:「創立百周年記念会館」講堂(3階)入口
受付時間は両日とも開催時刻の30分前より
参加費:1,000円(資料代)
プログラム:
3月25日(月)2018年度トルコ調査報告会
13:00 挨拶/阿部知之(中近東文化センター理事長)
13:10 アナトリア考古学研究所の活動(2018)
/大村幸弘(アナトリア考古学研究所長)
13:45 第10次ビュクリュカレ発掘調査
/松村公仁(アナトリア考古学研究所)
14:35 休憩
14:50 第33次カマン・カレホユック発掘調査
/大村幸弘( 同上 )
15:40 第10回ヤッスホユック発掘調査
/大村正子( 同上 )
司会:吉田大輔( 同上 )
17:00 懇親会
3月26日(火)トルコ調査研究会
司会:平井昭司
10:30 カマン・カレホユック遺跡出土遺物の物質科学的研究(26)
*ビュクリュカレ遺跡出土プラスター及び土器の産地推定に関する研究
/岩本翔太・阿部善也・中井泉(東京理科大学)
*カマン・カレホユック遺跡出土クリーム色土器の製作技術に関する研
究/村田美来・岩本翔汰・阿部善也・中井泉(東京理科大学)
11:20 質疑応答
11:30 休憩(10分)
—
司会:松村公仁
11:40 地中探査によるヤッスホユックも遺構分布調査のまとめ
/福田勝利(京都大学)
12:00 ヤッスホユック遺丘における王宮址の劣化状況調査
/鉾井修一(東南大学/京都大学)・福田勝利(京都大学)
12:20 質疑応答
12:30 昼食
—
司会:大村正子
13:30 豹型頭部像が出土したビュクリュカレ遺跡前2千年紀前半の建築遺構に
ついて/松村公仁(アナトリア考古学研究所)
13:50 ビュクリュカレ出土のヒョウ像の宗教的意義
/小板橋又久(都立立川高等学校)
14:10 Uncovering the Changes in the Technology of Pottery Production
at the Iron Age Yassıhöyük/Nurcan KÜÇÜKARSLAN (岡山大学)
14:30 カマン・カレホユック出土アリシャールⅣ式鹿文土器の研究—図像様式
及び出土層序による制作年代の想定—/水田徹(中近東文化センター)
14:50 質疑応答
15:00 休憩(20分)
—
司会:大村幸弘
15:20 中央アナトリアにおける製鉄文化解明の試み(10)—ヒッタイトの鉄と
は何か—/増渕麻里耶(東京文化財研究所)
15:40 カマン・カレホユック第Ⅲc層及び第Ⅳa層出土鉄関連資料から推定さ
れる鉄・鉄器生産活動/赤沼英男(岩手県立博物館)
16:00 質疑応答
16:10 閉会の挨拶/大村幸弘(アナトリア考古学研究所)
申込み:
3月20日(水)までに次の参加申し込みフォームよりお申し込みください。
http://www.jiaa-kaman.org/form_conf/application_conf_2018.html
定員(250名)になり次第、締め切らせていただきます。
問合せ:(公財)中近東文化センター附属アナトリア考古学研究所
181-0015 東京都三鷹市大沢3-10-31
TEL: 0422-32-7111(代表)
0422-32-7665(直通)
Email: tokyo@jiaa-kaman.org
ホームページ: http://www.jiaa-kaman.org
詳細は下記URLをご覧下さい。
http://www.jiaa-kaman.org/jp/conference_2018_2_1.html
2019年3月23日(土)開催:伝塾セミナー2019 第32回「失われた文化遺産−シリア紛争下の文化遺産を中心に−」
伝塾セミナー2019 第32回「失われた文化遺産−シリア紛争下の文化遺産を中心に−」が開催されます
名 称:伝塾セミナー2019 第32回「失われた文化遺産−シリア紛争下の文化遺産を中心に−」
趣 旨:
世界では、日々貴重な文化遺産が失われている。その原因は地震や火災、老朽化による取り壊し、経済開発、紛争や文化浄化など多岐にわたる。本発表では、失われた文化遺産とくにシリア紛争下の文化遺産を中心に取り上げたい。中東のシリアは、2011年3月に起きた大規模な民主化要求運動を契機に、内戦状態へと突入し、すでに8年の月日が経過している。シリア国内での死者は50万人に達し、500万人ものシリア国民が国外へと逃れている。このシリア内戦では多くの人命が損なわれているだけではなく、その被害はシリア国内の貴重な文化遺産にもおよんでいる。本発表では、まずシリア内戦下における文化遺産の被災の現状に関して報告し、その後、シリア内戦下で文化遺産を護っていく意義、シリア内戦終結後に文化遺産を復興する意味について考えたい。
主 催: 伝塾
日 時:3月23日(土)14:00〜16:30(13:30受付開始)
会 場:JICA地球ひろば:セミナールーム201AB
東京都新宿区市谷本村町10-5
https://www.jica.go.jp/hiroba/about/map/
受講料:各回2000円・学生(25歳以下)1000円
※当日受付にてお支払頂きます。
※学生の方は学生証持参御願いいたします。
講 師:安倍雅史(独立行政法人東京文化財研究所文化遺産国際協力センター研究員)
申 込:メールアドレス宛へ必要事項を明記の上、申し込みお願いいたします。
セミナー事務局宛: denjyuku.seminar@gmail.com
・お名前(フルネーム)
・開催月またはセミナーの回数(第何回か)
※複数回ご参加予定の場合も、参加予定の第何回かをお書きください。
※申し込み多数の場合は先着順とさせていただきます。
問い合わせ先:上記(申込先)に同じ。
詳細は下記URLをご覧下さい。
https://denjyuku.blogspot.com/2018/12/2019-13.html
2019年3月20日(水)開催:科研第3回研究会(特別講演会)「アナトリア古代史の諸問題:ビュクリュカレ遺跡発掘調査を通して」
A02-計画研究02 第3回研究会(特別講演会)
アナトリア古代史の諸問題:ビュクリュカレ遺跡発掘調査を通して
アナトリア考古学研究所の松村公仁先生をお迎えして、A02-計画研究02「古代西アジアにおける都市の景観と機能」の特別講演会を開催します。松村先生は長年アナトリア(現在のトルコ共和国)における発掘調査に携わっており、2009年度からはトルコの首都アンカラの南東約65kmに位置するビュクリュカレ遺跡の調査を指揮しています。同調査はヒッタイト粘土板文書片の発見など、非常に重要な成果を数多くもたらしており、トルコにおける遺跡調査の中でも最も注目を浴びている遺跡の一つに数えられます。講演会ではこの調査についてお話ししていただきます。
日時
2019年3月20日(水)16:00-18:00
会場
筑波大学総合研究棟B 110教室 (地図中J-6)
講師
松村 公仁 先生(アナトリア考古学研究所)
演題
「アナトリア古代史の諸問題:ビュクリュカレ遺跡発掘調査を通して」
コメンテーター
津本 英利 先生(古代オリエント博物館)
*参加自由、事前登録不要です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
下記ウェブサイトからもご覧いただけます。
なお、こちらからポスターをダウンロードできます。
日本語 http://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city/seminar/index.html
英語 http://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city_EN/seminar_EN/index_EN.html
皆様のご参加をお待ちしております。
お問い合わせ先
西アジア文明研究センター事務局 廣永・上原
**************************************************************************
科学研究費補助金 新学術領域研究(研究領域提案型)
「西アジア都市」事務室
〒305-8571 茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学人文社会科学研究科歴史・人類学専攻事務室付
西アジア文明研究センター
2019 年3 月17 日(日)開催:フェニキア・カルタゴ研究会 第5回公開報告会
フェニキア・カルタゴ研究会 第5回公開報告会
The Society for Phoenician and Punic Studies in Japan
今回のテーマは「古代地中海世界における人々の移動とネットワーク」です。今日のグローバル化した社会において、人々の移動がもたらす衝突や軋轢は、我々が直面する大きな課題でもあります。フェニキア人に代表される古代地中海世界の人々の経験が、現代の我々に訴えるものは何か、そのような視点も踏まえながら、多彩な報告をもとに考えてみたいと思います。会場後方には、ポスターや現地踏査の写真も掲示し、皆様との意見交換や歓談の場も計画しております。是非、多くの皆様のご参加をお待ちしております。
プログラム
12:30 開場
13:00 開会の辞
13:10 ①「古代地中海世界における人々の移動を考える」 長谷川岳男(鎌倉女子大学)
13:40 ②「フェニキアの海外発展−アイデンティティとネットワークの変容」佐藤 育子(日本女子大学)
14:10 ③「古代イベリア人とフェニキア、カルタゴ文化」 宮嵜 麻子(東洋大学)
14:40 休憩(15 分)
14:55 ④「古代ローマ帝国属州アフリカにおけるローマ人、ポエニ人、リビア人の関係について」青木 真兵(神戸山手大学)
15:25 ⑤「ギリシアにおけるフェニキア人についての叙述」 師尾 晶子(千葉商科大学)
15:55 ポスターセッション/フリートーキング
16:25 閉会の辞
16:30 閉会
日時:2019 年3 月17 日(日) 13:00〜16:30
場所:放送大学東京文京学習センター 多目的講義室1(地下鉄茗荷谷駅下車徒歩3分)
参加をご希望の方は、準備の都合上、3 月15 日(金)までに下記までお申込み下さい。
★連絡先 isatou@fc.jwu.ac.jp(佐藤まで)
*当日のご参加も歓迎いたします。
主催 フェニキア・カルタゴ研究会
科研費
18H03587 (基盤A 代表:周藤芳幸) 古代地中海世界における知の動態と文化的記憶
16K03131 (基盤C 代表: 佐藤育子) 地中海におけるフェニキア・カルタゴ文化の発展と変容
16K03122 (基盤C 代表:師尾晶子) 小アジアにおけるグローバル文化としてのギリシア文化とその地域性に関する研究
2019年3月17日(日)開催:計画研究01「西アジア先史時代における生業と社会構造」 第4回研究会(講演会)『埋葬から読み解く社会−アナトリア新石器時代葬制研究の最前線−』
新学術領域研究『都市文明の本質:古代西アジアにおける都市の発生と変容の学際研究』
A01-計画研究01「西アジア先史時代における生業と社会構造」
第4回研究会(講演会)
計画研究01「西アジア先史時代における生業と社会構造」では、トルコの人類学を牽引し第一線で活躍するY. S.エルダル教授を講師に迎え、講演会を開催します。
『埋葬から読み解く社会−アナトリア新石器時代葬制研究の最前線−』
講師:ユルマズ・セリム・エルダル(トルコ、ハジェテペ大学教授)
日時:2019年3月17日(日)14:00〜16:00
会場:筑波大学東京キャンパス(茗荷谷)119講義室
会場へのアクセスは、http://www.tsukuba.ac.jp/access/bunkyo_access.htmlの地図を参照ください。
【概要】
エルダル教授が主任を務めるハジェテペ大学人類学教室には、チャヨニュ、キョルティック・テペ、アシュックル・ホユックなど、トルコの著名な新石器時代の遺跡から出土した人骨が多数収蔵され、日々研究が進められています。それはまさに「宝の山」といった趣ですが、今回の講演ではその宝の山から何が見つかったのか、埋葬方法や副葬品にも目を配りながら、アナトリア新石器時代の埋葬伝統から見えてくる社会についてお話しいただきます。
*使用言語:トルコ語(日本語通訳あり)
*事前申し込みは不要です。
2019年3月15日(金)開催:計画研究01「西アジア先史時代における生業と社会構造」 第3回研究会(国際ワークショップ)
新学術領域研究『都市文明の本質:古代西アジアにおける都市の発生と変容の学際研究』
A01-計画研究01「西アジア先史時代における生業と社会構造」
第3回研究会(国際ワークショップ)
International Workshop
“What bone tells us: The Neolithic lifeways in Anatolia and beyond”あ
計画研究01「西アジア先史時代における生業と社会構造」では、以下の要領で国際ワークショップを開催します。
今回はトルコから3名の人類学者をお迎えし、国内の気鋭の研究者を交えて、「骨からわかること」と題して、食性、健康状態、人口構成など、多方面から新石器時代の人々の生活に迫ります。
日時:2019年3月15日(金)13:30 – 18:00
会場:筑波大学総合研究棟A107
会場については、以下のキャンパスマップをご参照ください
(http://www.tsukuba.ac.jp/access/map_central.html)
プログラム
13:30-13:40: Opening address Yutaka Miyake (University of Tsukuba)
13:40-14:10: Yuko Miyauchi (University of Tsukuba)
Reconsidering the infant burials in prehistoric West Asia: Case study from Tappeh Sang-i Chakhmaq, Iran
14:10-14:40: Osamu Kondo (University of Tokyo)
Paleobiology of the Neolithic people from Hasankeyf Höyük
14:40-15:10: Ömür Dilek Erdal (Hacettepe University, Turkey)
Population structure and health status of Aşıklı Höyük people
15:10-15:40: Coffee break
15:40-16:10: Yu Itahashi (University of Tokyo)
Change of the contributions of animal protein between hunter and herder in the Neolithic Anatolia
16:10-16:40: Kameray Özdemir (Hacettepe University)
From sedentary populations to centralized societies: Changing in dietary pattern in Anatolia
16:40-17:10: Yılmaz Selim Erdal (Hacettepe University)
Effect of agriculture on human skeleton: A bioarchaeological study in the Neolithic Anatolia
17:10-18:00: Discussion
18:00- : Reception
*発表はすべて英語でおこなわれます。
*事前申し込みは不要です。
2019年2月4日(月)開催:金沢大学藤井純夫先生最終講義
藤井純夫先生最終講義のお知らせ
ご参加の場合は以下にご連絡ください。
申込先: takuro.adachi@gmail.com
場 所:石川県政しいのき迎賓館 3階 セミナールームB
金沢市広坂2丁目1番1号 TEL : 076-261-1111
http://www.shiinoki-geihinkan.jp/about/access.html
日 程:2019年2月4日(月)13:00~14:30
主 催:金沢大学人文学類考古学研究室
13:00~14:20 藤井純夫先生最終講義
「Decades in Deserts: 西アジア遊牧社会の起源を求めて」
14:20~14:30 記念論集・記念品謹呈
懇親会
ご参加の場合はご連絡ください。
申込先: takuro.adachi@gmail.com
15:30~17:30 会 場:カフェ・アルコプレーゴ
(グループ名CAFFE ARCO di Campagneとも表示しています)
(金沢市片町1-3-21プレーゴ通り TEL 076-223-7333)
http://campagne.jp/arco/
懇親会参加費/一般 5000円、学部生・大学院生 3000円
2019年1月31日(木)開催:科研合同研究会「砂漠の中の庭園:エジプト・ダハシュールの屈折ピラミッドにおける近年の発掘調査」
A02-計画研究03・C01-計画研究05 第1回合同研究会:Special Lecture
「砂漠の中の庭園:エジプト・ダハシュールの屈折ピラミッドにおける近年の発掘調査」
計画研究03「古代エジプトにおける都市の景観と構造」および計画研究05「中世から近代の西アジア・イスラーム都市の構造に関する歴史学的研究」による第1回合同研究会(特別講演会)を開催します。
日時:2019年1月31日(木)17:30-19:00
会場:京都大学稲盛財団記念館 3F 中会議室
(京都市左京区吉田下阿達町46:京阪電車神宮丸太町駅から徒歩5分)
講師:フェリックス・アーノルド博士(マドリード・ドイツ考古学研究所 上席研究員)
Dr. Felix Arnold (German Archaeological Institute – Madrid Department)
演題:A Garden in the Desert: Recent Excavations at the Bent Pyramid in
Dahshur, Egypt
言語:英語(通訳はありません)
*参加無料・事前申込不要
共催:・京都大学アフリカ学際研究拠点推進ユニット・京都大学学術研究支援室・日本学術振興会カイロ研究連絡センター・金沢大学新学術創成研究機構
お問い合わせ先:京都大学学術研究支援室
075-753-5163(担当:坂本)