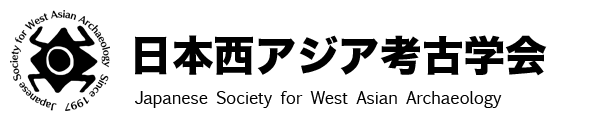2022年7月22日開催オンライン研究会”Exploiting Shells and Bones. Preliminary results from the study of some prehistoric and protohistoric productions in SouthWest Asia and Europe”
オンライン研究会の情報をいただきましたので、お知らせします。
***********************************
A01-計画研究01第19回研究会
計画研究01「西アジア先史時代における生業と社会構造」による第19回研究会を開催します。
日時:2022年7月22日(金)15:00-17:00
会場:Zoomを用いたオンライン開催
発表者:Dr. Laura Manca (National Museum of Natural History, Paris)
“Exploiting Shells and Bones. Preliminary results from the study of some prehistoric and protohistoric productions in SouthWest Asia and Europe”
※ オンライン参加をご希望の方は、7月19日(火)までにrcwasia[@]hass.tsukuba.ac.jp (「西アジア都市」事務局:土日は非対応)宛てのメールでご連絡ください。
新学術ホームページ
日本語 https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city/seminar/index.html#A01-01_19
English https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city_EN/seminar_EN/index_EN.html#A01-01_19
————————————————————————–
西アジア文明研究センター
廣永・上原
***********************************************************************
科学研究費補助金 新学術領域研究(研究領域提案型)
「西アジア都市」事務室
〒305-8571 茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学西アジア文明研究センター
029 853 5441
rcwasia@hass.tsukuba.ac.jp
2022年7月15日オンライン研究会「中央ユーラシアのオアシス都市と草原都市」
オンライン研究会の情報をいただきましたので、お知らせします。
***********************************
C01-計画研究05 第26回研究会
計画研究05「中世から近代の西アジア・イスラーム都市の構造に関する歴史学的研究」による第26回研究会を開催します。
「都市とは何か」を検討するにあたり、さまざまな地域や時代の歴史をご専門とされる先生方をお招きして、オンライン(Zoom)による連続講演会「都市の世界史」を開催しております。
第4回は下記の要領で行います。
日時:2022年7月15日(金)19:30~21:00
講師:森安 孝夫先生(大阪大学)
テーマ:「中央ユーラシアのオアシス都市と草原都市」
【講師紹介】
(公財)東洋文庫監事、大阪大学名誉教授。専門は仏教・マニ教時代の中央ユーラシア東部の歴史と古ウイグル文献学。専門書に『東西ウイグルと中央ユーラシア』(名古屋大学出版会、2015年)、Corpus of the Old Uighur Letters from the Eastern Silk Road (Berliner Turfantexte 46, Turnhout: Brepols, 2019)
などがあり、概説書に『シルクロードと唐帝国』(講談社学術文庫、2016年)、『シルクロード世界史』(講談社選書メチエ、2020年)がある。
*今回は、イスラム化以前の中央ユーラシア東部の都市の典型として、オアシス都市と草原都市があること、農耕定住民の築いたオアシス都市は紀元前から存在するも、紀元後に現れる草原都市の成立にはいくつかの要因があり、そこでは騎馬遊牧民と農耕定住民の共生関係が見られたことなどをお話しいただきます。
申込先: https://forms.gle/BUwxUD3zcgALFXbB9
*Googleフォームでの申し込みとなります。前日の7月14日正午までに、上記のURLからお申し込みください。
*お申し込みいただいた方へ、前日中に、当日のURL(Zoom)をお送りいたします。
本連続講演会は、新学術領域研究「都市文明の本質:古代西アジアにおける都市の発生と変容の学際研究」計画研究「中世から近代の西アジア・イスラーム都市の構造に関する歴史学的研究」(代表:守川知子)にて行ってきた「西アジア都市研究」を発展させたものです。
ご講演は45~50分、質疑応答は40~45分と、ディスカッションを重視した時間配分となっております。
奮ってご参加くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
【これまでの講演会】
第1回・4月22日(金) 深見奈緒子先生(日本学術振興会カイロ研究連絡センター)「都市の歴史:生態圏と形態・人口」
第2回・5月24日(火) 森本公誠先生(東大寺)「アラブの軍営都市(ミスル)」
第3回・6月21日(火) 菅谷成子先生(愛媛大学)「スペイン植民地都市マニラ」
【今後の予定】
第5回・9月28日(水) 稲葉穣先生(京都大学)
第6回・10月 深沢克己先生(東京大学)
第7回・11月 松井洋子先生(東京大学)
第8回・12月 常木晃先生(筑波大学)
皆様のご参加をお待ちしております。
守川知子
tomomo[a]l.u-tokyo.ac.jp
新学術ホームページ
日本語 https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city/seminar/index.html#C01-05_26
English https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city_EN/seminar_EN/index_EN.html#C01-05_26
———————————————————————————————————————
新学術「西アジア都市」総括班事務局
**************************************************************************
科学研究費補助金 新学術領域研究(研究領域提案型)
「西アジア都市」事務室
〒305-8571 茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学西アジア文明研究センター
029 853 5441
rcwasia@hass.tsukuba.ac.jp
2022年6月19日開催研究会:アコリス考古学プロジェクト2022
研究会の案内をいただきましたので、お知らせします。
***********************************
エジプト・アコリス遺跡考古学調査団では、下記の通り公開シンポジウムを開催いたします。
オンライン(Zoomミーティング)での参加をご希望の方は、【6月18日(土)17:00まで】に【yoshisuto@nagoya-u.jp(周藤芳幸)】までご連絡ください。招待URL等をご案内いたします。
日時:2022年6月19日(日) 13:00-18:30
会場:名古屋大学文学部237講義室(zoomミーティングでのハイブリッド開催)
参加費:無料
主催:アコリス遺跡考古学調査団、名古屋大学人類文化遺産テクスト学研究センター
アコリス考古学プロジェクト2022
13:00-13:05 開会の辞
13:05-13:25 小林 卓「ローマ帝政期における太陽神崇拝とミトラス教」
13:25-13:45 讃岐 綾奈「ヘレニズム期ロドスの組合と外国人」
13:45-14:15 伊藤 早苗「アッシリア帝国の使者と幹線道路研究」
(休憩)
14:20-14:50 清水 麻里奈「アコリス遺跡におけるワニの壁龕とその類例」
14:50-15:20 小川 拓郎「ニューメニア採石場址N区周辺の採石過程の復元的考察」
15:20-15:50 周藤 芳幸「ニューメニア採石場址の横穴ギャラリー」
15:50-16:20 辻村 純代「2017年度出土ミイラのCT解析結果」
(休憩)
16:30-17:00 黒沼 太一「先王朝-初期王朝時代のゲベレイン遺跡:近年の調査成果から」
17:00-17:30 小野塚 拓造「南レヴァントにおける青銅器・鉄器時代移行期の様相」
17:30-18:00 津本 英利「西アジア鉄器時代移行期の鉄器使用状況に関する最近の研究」
18:00-18:30 総合討論
※参加希望の方は、周藤芳幸(yoshisuto@nagoya-u.jp)までご連絡ください。
※参加者名は、本名、フルネームで表示されるよう設定してください。
※発表資料の録画、録音、スクリーンショット等はお控えください。
2022年5月2日~5日上演:『ギルガメシュ叙事詩』公演
『ギルガメシュ叙事詩』公演の開催案内をいただきましたので、お知らせします。
***********************************
SPAC-静岡県舞台芸術センターは、静岡を拠点に活動する専属の劇団として、舞台作品の創造や国内外での公演活動と同時に、劇場の企画・運営を行っています。
この度、ゴールデンウィークに新緑あふれる駿府城公園(静岡市内)にて『ギルガメシュ叙事詩』公演を開催する運びとなりました。本公演は先月末にフランス国立ケ・ブランリー美術館にて公演し、好評を博しました。今回は、待望の凱旋公演です。
SPAC-静岡県舞台芸術センター 『ギルガメシュ叙事詩』日本語上演/英語字幕
5/2(月)18:40、3(火・祝)18:40、4(水・祝)18:40、5(木・祝)18:40
駿府城公園 紅葉山庭園前広場 特設会場
台本・演出:宮城聰
翻訳:月本昭男(ぷねうま舎刊『ラピス・ラズリ版 ギルガメシュ王の物語』)
音楽:棚川寛子
人形デザイン:沢則行
特設ページ:
https://festival-shizuoka.jp/program/the-epic-of-gilgamesh/
▼チケット販売状況はこちら
https://spac.or.jp/news/?p=21396
▼「ふじのくに⇄せかい演劇祭」と一緒に「ストレンジシード静岡」も合わせてお楽しみいただけます。
⇓「ストレンジシード静岡」の詳細はこちら⇓
https://www.strangeseed.info/
そのほか「広場トーク」、しりあがり寿さんによる「しりあがり寿presents ずらナイト」も同時開催しております。
初夏の静岡へぜひお越しください!
2022年4月22日開催オンライン研究会「都市の歴史:生態圏と形態・人口」
オンライン研究会の案内をいただきましたのでお知らせします。
***********************************
C01-計画研究05 第23回研究会
計画研究05「中世から近代の西アジア・イスラーム都市の構造に関する歴史学的研究」による第23回研究会を開催します。
このたび、「都市とは何か」を検討するにあたり、さまざまな地域や時代の歴史をご専門とされる先生方をお招きして、連続講演会「都市の世界史」をZoomオンラインにて開催する運びとなりました。
第1回は下記の要領で行います。
日時:2022年4月22日(金)19:30~21:00
講師:深見奈緒子先生(日本学術振興会カイロ研究連絡センター)
テーマ:「都市の歴史:生態圏と形態・人口」
申込先:https://forms.gle/baJ8GdsXa5ABgm4DA
*Googleフォームでの申し込みとなります。前日の4月21日までに、上記のURLからお申込みください。
*お申し込みいただいた方へ、後日、当日のURL(Zoom)をお送りいたします。
本連続講演会は、計画研究C01-05「中世から近代の西アジア・イスラーム都市の構造に関する歴史学的研究」にて行ってきた「西アジア都市研究」を発展させたものです。
ご講演は45~50分、質疑応答は40~45分と、ディスカッションを重視した時間配分となっております。
奮ってご参加くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
*第2回以降は、以下のような予定です。
第2回・5月24日(火):森本公誠先生(東大寺)
第3回・6月:菅谷成子先生(愛媛大学)
第4回・7月:森安孝夫先生(大阪大学)
第5回・9月:稲葉穣先生(京都大学)
守川知子
tomomo[@]l.u-tokyo.ac.jp
新学術ホームページ
日本語 https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city/seminar/index.html#C01-05_23
English https://rcwasia.hass.tsukuba.ac.jp/city_EN/seminar_EN/index_EN.html#C01-05_23
————————————————————————–
皆様のご参加をお待ちしております。
西アジア文明研究センター
上原・廣永
***********************************************************************
科学研究費補助金 新学術領域研究(研究領域提案型)
「西アジア都市」事務室
〒305-8571 茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学西アジア文明研究センター
029 853 5441
rcwasia@hass.tsukuba.ac.jp
2022年3月19日開催成果報告会「世界の古代文明を探る」
オンライン報告会の案内をいただきましたのでお知らせします。
***********************************
金沢大学超然プロジェクト「古代文明の学際研究の世界的拠点形成」成果報告会「世界の古代文明を探る」
超然プロジェクト「古代文明の学際研究の世界的拠点形成」は、金沢大学が取り組む世界の古代文明の考古学的研究を先鋭化し、自然科学との学際融合研究と「文化資源マネジメント」の取り組みを糾合させる国際的な研究拠点を形成するため、2019年度より実施してまいりました。このたび、プロジェクトの期間満了を迎えるにあたり、過去3か年の成果を研究・大学関係者のみならず市民の皆様にもお知らせするべく、プロジェクト参画者の集う報告会を以下の通り開催いたします。会場の公開だけでなく、オンラインでのライブ配信も行ないますので、奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。
日時:2022年3月19日(土)13:00-17:30(12:45開場)
会場:金沢市文化ホール 2F 大集会室(https://www.bunka-h.gr.jp/access/)
主催:金沢大学超然プロジェクト「古代文明の学際研究の世界的拠点形成」(代表:河合 望)
共催:金沢大学人間社会研究域附属 古代文明・文化資源学研究センター、金沢大学新学術創成研究機構 文化遺産国際協力ワーキングユニット
問い合わせ:ku.ancient@gmail.com
*参加方法*
会場参加(申込順60名まで)・オンライン視聴(Zoomウェビナー)ともに事前のお申し込みが必要です。
お申し込みはこちら→ https://peatix.com/event/3153149(3月18日(金)13:00まで)
※ Peatixへの登録が必要です(無料)
※ 感染症等の状況により会場での参加を制限させていただく場合があります
*プログラム*
13:00-13:10 開会挨拶/趣旨説明
13:10-13:30 報告① 上杉彰紀(金沢大学)
「インダス文明のダイナミズム:文明社会の仕組みを地域間交流から考える」
13:30-13:50 報告② 小髙敬寛(金沢大学)
「文明前夜のメソポタミア東縁部:シャフリゾール平原の先史遺跡調査」
13:50-14:10 報告③ 藤井純夫(金沢大学)
「パンサー・トラップ:アラビア半島先史遊牧民の生捕り装置」
14:10-14:30 報告④ 河合 望(金沢大学)
「エジプト、北サッカラ遺跡の発掘調査の意義と今後の展望」
14:45-15:05 報告⑤ 関 雄二(国立民族学博物館)
「ペルー北高地パコパンパ遺跡における防御遺構:インカと在地社会」
15:05-15:25 報告⑥ 中村誠一(金沢大学)
「マヤ文明の謎に挑む−世界遺産「コパンのマヤ遺跡」の発掘調査−」
15:25-15:45 報告⑦ 石村 智(東京文化財研究所)
「南海の文明−文明の崩壊と持続可能性について−」
15:45-16:05 報告⑧ 覚張隆史(金沢大学)
「難古代ゲノム解析資料群を対象とした新しい分析手法の開発」
16:05-16:25 報告⑨ 足立拓朗(金沢大学)
「『北陸と世界の考古学』における「文明と王権」」
16:40-17:20 質疑応答
17:20-17:30 閉会挨拶
詳細はこちら(PDFチラシあり)
https://csac-cr.w3.kanazawa-u.ac.jp/…/sympo20220319.html
2022年2月24日開催オンライン講演会「「末期王朝期およびプトレマイオス朝初期におけるエジプトの政治・経済の発展:パピルス文書から分かること」」
オンライン講演会の案内をいただきましたのでお知らせします。
***********************************
京都エジプト学コロキウム 第2回講演
日時:2022年2月24日(木)11:30-12:30(日本時間)
会場:Zoomによるオンライン開催
講演者:アンドリュー・ホーガン(カリフォルニア大学バークレー校、テブトゥーニス・パピルス文書研究所)
題目:「末期王朝期およびプトレマイオス朝初期におけるエジプトの政治・経済の発展:パピルス文書から分かること」
※ 講演は英語で行われます。
※ オンライン参加をご希望の方は、以下のアドレスからご登録ください。
https://www.kyoto-egyptology.de/
古代エジプトの死後の世界とジェンダーに関する第1回講演 (Gender and the Egyptian Afterlife) は3月4日の18時からに延期されました。こちらもまだ登録できますので、上記のページからご登録ください。
2022年3月6日オンライン開催「フェニキア・カルタゴ研究会第7回公開報告会」
オンライン研究会の案内をいただきましたのでお知らせします。
***********************************
フェニキア・カルタゴ研究会第7回公開報告会
3月6日(日)(Zoomによるオンライン)
昨年度に引き続き、今年度もオンラインでの公開報告会を下記の要領で実施いたします。
前半では、フェニキア史の周辺ともかかわる古代オリエント史の分野からの発表に加え、西方フェニキア人社会の重要な拠点、サルデーニャ島のポエニ文化について考察します。
後半では、カルタゴにも関係する古代北アフリカの農業について、新たな科研のテーマをもとにした研究成果の発表も盛り込みました。さまざまな方向性からフェニキア・カルタゴ研究の「今」に迫りたいと思います。是非、多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。
申込先は以下の通りです。
参加をご希望の方は、3月4日(金)までに下記のフォームからお申込み下さい。3月5日(土)までに当日のリンク先など参加方法をお知らせします
https://forms.gle/LZB7PNCpRQi8UqLf6
プログラム
13:15 入室開始
13:30 開会の辞・第1部趣旨説明 佐藤 育子(日本女子大学)
13:40 「都市アッシュルにおけるエジプト人アーカイブに関する一考察」丸小野 壮太(常磐大学高等学校)
14:15 「サルデーニャ島におけるポエニ文化:前6−前3世紀を中心に」青木 真兵(関西大学)
14:50 休憩(10分)
1500 第2部趣旨説明 大清水 裕(滋賀大学)
15:05 「後2世紀属州アフリカの皇帝所領における農業経営と小作人を取り巻く権利関係」宮坂 渉 (筑波大学)
15:40 ディスカッション
16:00 閉会
主催 フェニキア・カルタゴ研究会
JSPS科研費
21H00584(研究代表者 大清水裕)
古代ローマ期北アフリカの農業に関する学際的研究
20K01237(研究代表者 宮坂渉)
古代ローマにおける取引実務の実像と担保法理論への影響に関する研究
16K03131(研究代表者 佐藤育子)
地中海におけるフェニキア・カルタゴ文化の発展と変容
発表要旨
丸小野報告
前1千年紀前半において古代東地中海世界を支配した新アッシリア帝国はアッシリア人だけではなく、フェニキア人、アラム人、エジプト人など様々な出自を持つ人々によって構成されていた。近年、都市アッシュルにおけるエジプト人アーカイブに関して言及した先行研究[Karlsson, M.(2021a・2021b)、Höflmayer, F. (2021)、Wasmuth, M. (2021)]が複数出版されている。そこで、本発表では2020年に提出した卒業論文『新アッシリア帝国とエジプト人ー都市アッシュルにおけるエジプト人に関する考察ー』を2021年に出版された先行研究も踏まえ、都市アッシュルにおけるエジプト人アーカイブに関する一考察を行う。
青木報告
私の研究目的は、西地中海においてカルタゴの支配下にあったフェニキア植民都市への分析を通じて、カルタゴからローマへと支配者が変わっていく西地中海世界の様子を地域の視点から明らかにすることである。
以前、この観点から新ポエニ語とラテン語の二言語併用碑文への分析を通じて、サルデーニャ島の「ローマ化」の一側面を考察した※。この考察では、二言語併用碑文においてラテン語には刻まれず、新ポエニ語にのみみられるフェニキアの神への献辞があったことが分かった。本発表では「ローマ化」以前の状態を明らかにするため、サルデーニャ島におけるポエニ文化について、フェニキア人と現地コミュニティの関係を通じて考察する。
※拙稿「サルデーニャ島のフェニキア人と『ローマ化』—都市スルキスの二言語併用碑文から—」『駒沢史学』84号、133-145頁、2015年。
宮坂報告
19世紀末から20世紀初めにかけて北アフリカ(チュニジア、アルジェリア)で相次いで出土した石碑文は、紀元後2世紀の元老院属州アフリカにおける皇帝所領での農業経営に関する貴重な情報を伝えている。例えば、小作人coloni−「賃借人conductores」−所領管理人procuratores−皇帝という重層構造、小作人からの請願とこれを処理するプロセス、多様な作物と土地利用、小作人に課される賃料と賦役等である。とりわけ、碑文に見られる所領管理人からの書簡において言及され、土地の利用と土地に対する権利関係とを規定すると考えられるlex Hadriana(LH)については、その内容と、関連するlex Manciana(LM)との関係性とが、Rostovtzeff、Flach、Kehoeらによって盛んに議論されてきた。本報告では、LHとLMに言及する碑文を紹介し、当時の農業経営と小作人を取り巻く権利関係を概観する。なお、1999年にはさらにLHに言及する碑文が、2013年と2016年にはLHの文言そのものを伝えるとされる碑文が出土しており、今後も議論の進展が期待される。
2022年2月18日開催オンライン懇話会「中世イスラム医学の外科治療としての焼灼とその東伝:10世紀医学書、11世紀アンダルス裁判事例集、12世紀『ホラズムシャーの宝庫』、そして『回回薬方』の記述から」
オンライン懇話会の案内をいただきましたのでお知らせします。
***********************************
日本学術振興会カイロ研究連絡センター定例懇話会(Zoom)のご案内
前略、カイロでは寒さも少しずつ和らぎ始めたかのように感じるこの頃です。この度は、中世アラブの医療とその伝播について尾崎先生にお話いただけることとなりました。ちなみにカイロのイスラーム美術館にも、数多くの医薬道具が展示されております。尾崎先生は、中世アラブを中心として、医薬に限らず食文化にもご造詣が深く、多数の論文を執筆していらっしゃいます。ぜひ、多くのみなさまにご参加いただきたく、ご案内いたします。オンラインの開催となりますので、お手続きのほど、よろしくお願いいたします。
◆ 日時:2022年2月18日(金曜) 開始時間:日本時間20時より (カイロ13時より) 60分
質疑応答:30分
◆ 配信方法:Zoom
◆ 講演:「中世イスラム医学の外科治療としての焼灼とその東伝:10世紀医学書、11世紀アンダルス裁判事例集、12世紀『ホラズムシャーの宝庫』、そして『回回薬方』の記述から」
◆ 講師:尾崎貴久子 (防衛大学校総合教育学群外国語教育室・教授)
◆ 要旨(講師記)
イスラム医学の外科治療の1つに焼灼がある。焼灼治療は、ハディースにおいては預言者ムハンマドが治療方法として挙げた3つの治療の1つであると記録されている。このことから、イスラム成立以前から人々に身近な治療であったといえる。
イスラム医学の焼灼治療の体系化は、10世紀、それぞれバグダードとコルドバで活躍した宮廷医師2人によってなされた。14世紀末には、このイスラム医学の焼灼法は、漢語イスラム医学書に「灸」として記載された。今回の発表では、まずイスラム医学の外科術や焼灼治療を、医学者や市井の人々はどのように認識、利用していたかを、10世紀の医学書および11世紀アンダルスの裁判事例集における医療裁判記録、そして14世紀に体系化された預言者の医学の書から検討する。
次に、焼灼法は東西イスラム世界の各地に伝播するが、その東への経路を考察する。最古のペルシャ語医学書とされる12世紀の『ホラズムシャーの宝庫』そして14世紀末の漢語医学書の『回回薬方』の記述を取り上げ、検討をおこなう。アラビア語・ペルシャ語・漢語の記述の比較検討からは、文字情報によるイスラム医学の東伝の時期と経路、その特徴が、さらには中国でのイスラム医学の治療者たちの活動の一端が浮かび上がる。
●参加方法:講演は無料となっております。参加者は、講演タイトル、氏名(フルネーム)と所属を明記の上、メール(jspslecmet@gmail.com)にて、前日までに必ずお申込みください。
ZoomのURL、ID、パスワードをこちらより後日連絡いたします。
※今回の講演は金曜に開催いたしますので、曜日をお間違えの無いようにご注意ください。
**********************************
日本学術振興会カイロ研究連絡センター
JSPS Cairo Research Station
Flat no.4, 9 al-Kamil Muhammad Street
Zamalek, Cairo, Egypt
Tel. Fax. 02-2736-3752
**********************************
深見奈緒子
Naoko Fukami
Director
トップ
トップ
9, Al-Kamel Muhammad St, Flat No4, Zamalek, Cairo, Egypt
Tel & Fax;office +20-2-2736-3752
Tel & Fax;home +20-2-2736-4728
E-mail: naokofukami@gmail.com
トップ
2022年7月18日開催「第15回ヨルダンの歴史と考古学に関する国際会議」
「第15回ヨルダンの歴史と考古学に関する国際会議」の情報をいただきましたので、お知らせします。
***********************************
先日ヨルダン大使館から来年(2022年)7月18日から21日までヨルダンヤルムーク大学で開催される
The 15th International Conference on the History and Archaeology of Jordan (ICHAJ 15)
の案内が届きました。
2022年2月19日オンライン開催:Online International Conference for the Iranian Archaeological Webinar, 2022
オンラインによる国際会議の案内をいただきましたので、お知らせします。
***********************************
昨年度に続き、駐日イラン大使館の主催でイランと日本の考古学者によるオンライン国際会議を開催することになりました。継続的にこのような国際会議を開催し、イランと日本の研究の協力関係を構築していくことが目的です。Zoomによるオンライン開催です。
事前にお名前(仮名可)とメールアドレスを登録すれば、どなたでも視聴することができます。是非、ご視聴をご検討ください。
日時:2022年2月19日(土)、15時30分~19時15分
開催方法:Zoom配信
申込:事前申込制
以下のWebsiteからお申し込みください。
https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_UMFpWkY9RDu4n9C5bvYlAw
参加費 :無料
言語:英語のみ
主催:駐日イラン大使館・The Research Institute of Cultural Heritage and Tourism (RICHT)
共催:金沢大学国際文化資源学研究センター
問い合わせ:takuro.adachi@gmail.com
Online International Conference for the Iranian Archaeological Webinar, 2022
Sponsorship: Embassy of Islamic Republic of Iran in Japan and Research Institute of Cultural Heritage and Tourism (RICHT).
Co-sponsorship: Center for the Study of Ancient Civilizations and Cultural Resources, Kanazawa University.
Endorsement: Tokyo National Research Institute for Cultural Properties; The Ancient Urbanization and Long-Distance Trades of Nomadic Pastoralism in West Asia (19H05033), Kanazawa University; Construction of the Basis for Empirical Research on State Formation Process in Human history (20K01092), Hiroshima University.
Date: 2022/ 19/ Feb. (Sat.) 15:30-19:15 (Japan Standard Time).
10:00-13:45 (Iran Standard Time)
*There is a 5.5 hour time difference between Iran and Japan.
Language: English; Online Environment: Zoom (host: Center for the Study of Ancient Civilizations and Cultural Resources, Kanazawa University).
Register in advance for the conference here by February 16th:
URL: https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_UMFpWkY9RDu4n9C5bvYlAw
Contact by e-mail: takuro.adachi@gmail.com
Program
15:30-15:35 (10:00- 10:05)
Welcome Speech
Morteza Rahmani Movahed (Ambassador of Islamic Republic of Iran, Embassy in Japan)
15:35-15:40 (10:05- 10:10)
Opening Address
Takuro Adachi (Professor, Kanazawa University)
15:40-16:00 (10:10- 10:30)
The Archaeology of Sistan Plain during the Bronze Age.
Rouhollah Shirazi (Associate Professor, University of Sistan and Baluchestan)
16:00-16:20 (10:30- 10:50)
Archaeological Survey in Khatam District, Yazd province.
Mohammad Hossein Azizi Kharanaghi (Assistant Professor of Iranian Center for Archaeology (ICAR), Research Institute of Cultural Heritage and Tourism)
16:20-16:40 (10:50-11:10)
The 8.2 ka Event and Re-microlithization in Southern Zagros.
Masashi Abe (Senior Researcher, Tokyo National Research Institute for Cultural Properties)
16:40-17:00 (11:10-11:30)
The Pleistocene Occupations in Northern Littoral and Hinterland of Persian Gulf and Oman Sea.
Sepehr Zarei (General Office of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Hormozgan Province)
17:00-17:10 (11:30-11:40) Break
17:10-17:30 (11:40-12:00)
Final Process of Painted Pottery Tradition: Review of Bronze Age Cultural Transition at Tappeh Anjirab, Gorgan Plain
Yui Arimatsu (Associate Professor, Hiroshima University)
17:30-17:50 (12:00-12:20)
Managing Preservation and Restoration in Archeological Sites and Sustainability.
Fariba Karimi (Researcher, Ministry of Heritage)
17:50-18:10 (12:20-12:40)
Erasing the Past: Re-engraved Bas-reliefs and Inscriptions during the Parthian Period.
Seiro Haruta (Professor, Tokai University)
18:10-18:30 (12:40-13:00)
Archaeological Survey of the Sham Valley during Ilkhanid Period, in the Culture Area of Aras, Northwest of Iran.
Soraya Afshari (Iranian research center for Archaeology (ICAR))
18:30-18:40 (13:00-13:10) Break
18:40-19:10 (13:10-13:40) Discussion
19:10-19:15 (13:40-13:45)
Closing Address
Saeed Banihashemi (Research chancellor of the embassy of the Islamic Republic of Iran in Japan)
2022年2月20日オンライン開催研究会「考古学と国際貢献:イスラエルの考古学と文化遺産」
***********************************
東京文化財研究所 研究会「考古学と国際貢献:イスラエルの考古学と文化遺産」開催のお知らせ【申込締切:2月17日 (木)】
●名称:研究会「考古学と国際貢献:イスラエルの考古学と文化遺産」
●主催:東京文化財研究所文化遺産国際協力センター
●趣旨:
文明揺籃の地である西アジア地域には多くの考古遺跡が存在し、欧米を中心とした調査隊が19世紀から発掘調査を行ってきました。同地域に対しては日本も同様に調査研究の膨大な蓄積があり、さらに近年では、遺跡を有する国の研究者が主体となった調査も盛んに行われるようになっています。今年度研究会ではイスラエルを対象に、同国の実務者より国立公園として進められている史跡整備の現状について、また日本国内の研究者から同国の考古学および関連分野の研究について講演いただくとともに、「考古学と国際貢献」についてディスカッションを予定しております。
●日時:2月20日(日)14:00-17:05
●プログラム:
14:00 開会挨拶
齊藤孝正(東京文化財研究所 所長)
14:05 趣旨説明
金井健(東京文化財研究所文化遺産国際協力センター保存計画研究室長)
14:15 イスラエル国立公園における考古遺跡の管理
ゼエヴ・マルガリート(イスラエル国立公園局保存開発部長)
14:45 ローマ時代初期のガリラヤ地方—考古学的視点から—
ドロール・ベン=ヨセフ(イスラエル国立公園局北部地区担当官)
15:15 日本の調査隊によるイスラエルの考古学調査の歴史
間舎裕生(東京文化財研究所文化遺産国際協力センターアソシエイトフェロー)
15:35 イスラエルの文化遺産マネジメントにおける国立公園制度の役割
岡田真弓(北海道大学観光学高等研究センター准教授)
15:55 イスラエルにおける遺跡保存と活用の課題—テル・レヘシュの例から—
長谷川修一(立教大学文学部キリスト教学科教授)
16:15 パネルディスカッション「考古学と国際貢献」
モデレーター:長谷川修一
パネリスト:ゼエヴ・マルガリート、ドロール・ベン=ヨセフ、岡田真弓、間舎裕生
17:00 閉会挨拶
友田正彦(東京文化財研究所文化遺産国際協力センター長)
●開催方式:オンライン(Zoomウェビナー)
●参加費:無料・事前申込制
●申込方法:
2月17日(木)までに下記フォームよりご登録ください。
●問合せ先:
東京文化財研究所文化遺産国際協力センター保存計画研究室
cds_jcicc@tobunken.go.jp